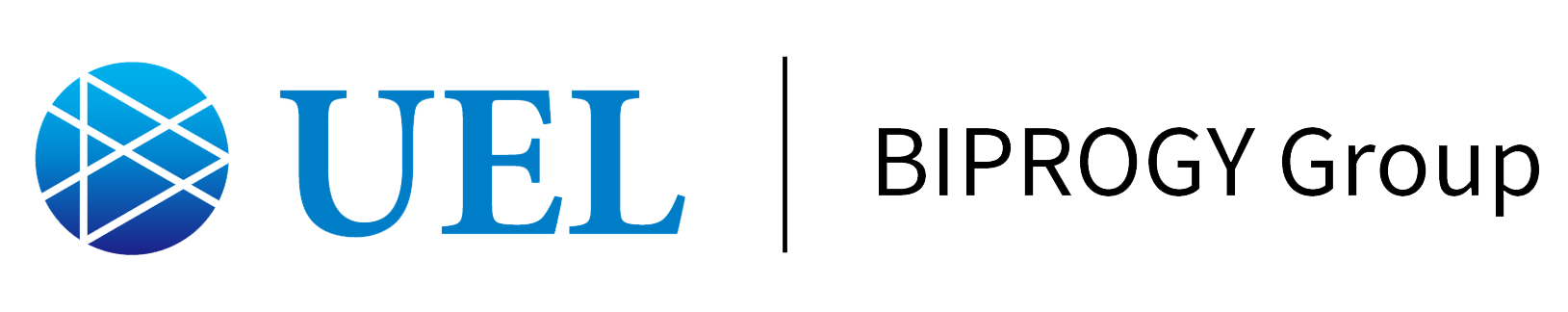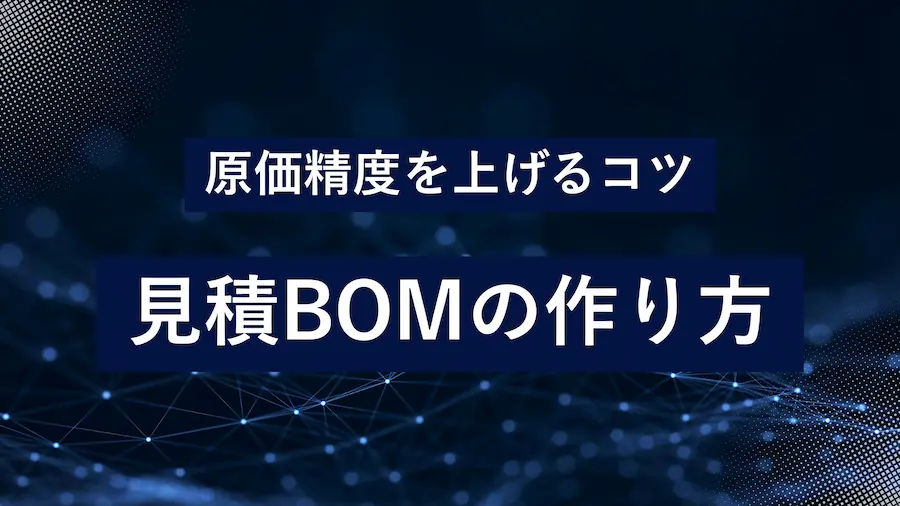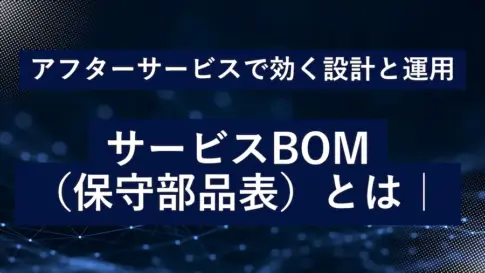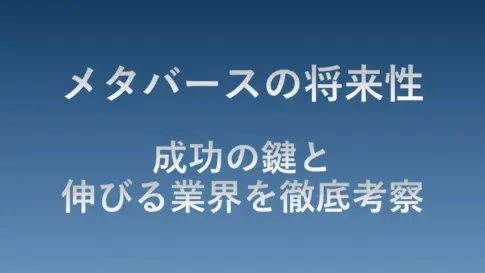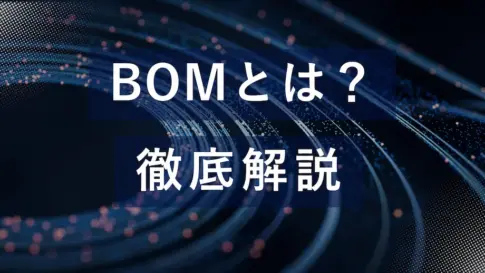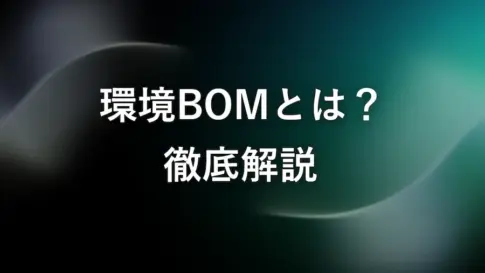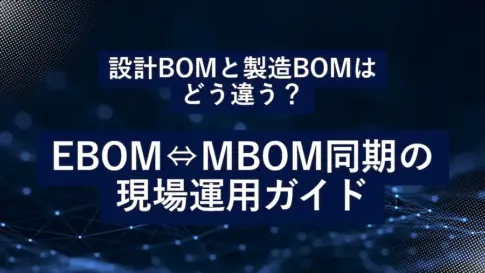「見積に時間がかかる」
「構成の粒度が人によってバラバラ」
「出した価格が、あとで原価割れしていた」
「見積もりのタスクが明確化されていなく、変更時の追跡が困難」
そんな見積業務の悩み、感じたことはありませんか?
営業や原価担当、設計、生産技術、購買など、見積に関わる部門は多岐にわたります。
しかし、製品構成や原価の前提条件がバラついていると、どれだけ努力してもスピードも精度も上がりません。
そこで注目されているのが、見積専用の部品表「見積BOM(Sales/Quote BOM)」です。
これは、設計用のEBOMや製造用のMBOMとは異なり、見積に最適化されたBOM構成を組むことで、工数を減らしつつ原価精度を向上させる仕組みです。
本記事では、以下の3ステップで見積BOMの作り方を分かりやすく解説します。
- ① 粗構成:ヒアリングや仕様書から部品群をざっくり洗い出す
- ② 標準化:社内品番や属性を整備し、構成のブレを防ぐ
- ③ 原価計算:Excelでロールアップし、粗利シナリオ別に価格試算
BOMに関して全体像を知りたい方はこちらの記事をごかくにんください。
→BOMとは?|定義・種類・作成手順・管理ベストプラクティスまで徹底解説
「スピード」と「精度」、どちらもあきらめない見積業務を目指したい方は、ぜひこの先を読み進めてみてください。

監修・執筆:UEL株式会社編集部
UEL株式会社のTechデザイン企画部と現場に精通した社内有識者が監修・執筆しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の企業・環境・状況への適用や効果を保証するものではありません。内容の利用は読者ご自身の判断と責任にてお願いいたします。参考としてご活用ください。
目次
見積BOMとは
見積BOM(Sales BOM/Quote BOM)とは、製造前の見積段階において使用される、見積用に最適化された部品表です。
その主な目的は、以下の3点に集約されます:
- 見積スピードの向上
- 原価精度の向上
- 見積条件や構成の一元化
つまり、「素早く・正確に・誰が見ても同じ条件で」見積を出せる仕組みを支えるのが、見積BOMの役割です。
この見積BOMを活用するのは、営業部門だけではありません。
実際には、以下のような複数部門が連携して活用することが想定されます:
- 営業/営業技術:初期見積や受注提案用に活用
- 見積・原価担当:製造原価や販管費を加味した試算に活用
- 設計部門:設計情報の参照・監修
- 生産技術/購買:調達可能性や製造性の視点でチェック・反映
EBOM(設計BOM)が設計上の完全構成、MBOM(製造BOM)が現場実行用の詳細構成だとすると、
見積BOMはその中間に位置する見積業務に最適化された構成といえます。
EBOMの概念構成をもとにしつつ、MBOMほど細かく分解しすぎないことで、
見積時点でも工数過多にならず、かつ精度ある原価試算が可能となります。
前提データ
見積BOMを正しく、効率的に作成するには、事前に揃えておくべき基本データがいくつかあります。
これらの整備が不十分なまま構成を進めると、原価精度のブレや手戻りが発生しやすくなるため、最初の準備が成功のカギを握ります。
見積BOM作成に必要な4つの前提条件
- 品目マスタ
品番、品名、カテゴリ、単位(UoM)、標準原価、調達区分(Make/Buy)などの基本情報。既存の部品や購入品は、登録漏れがないように事前棚卸を。 - レート情報
労務費・外注費のレート、オーバーヘッド(OH)率、販管費率(SGA)、為替レート、物流単価、関税率など。見積ロールアップに必要な係数を、カテゴリ別に定義しておくことが重要です。 - 見積条件
数量階段(Qty Break)、MOQ(最小発注数量)、LT(リードタイム)、保証範囲、適用日など。見積時点での前提条件を明文化しておくと、見積比較や更新が容易になります。 - 構成ルール
共通部品・代替品の扱い、キット化の方針、歩留まりの考え方、ファントム品の展開有無など、構成や原価計算に影響する社内ルールを明確にします。
「最低限の入力セット」を定義しておく理由
社内でBOMや原価構成を扱う際、「どこまで入力すればよいか」が曖昧なままでは、チーム間での精度や粒度がブレてしまいます。
そこで、自社にとっての最低限の入力項目セットを定義しておくことが推奨されます。
例えば以下のような項目が基本となります:
- 品番/品名/カテゴリ/標準原価/調達区分
- 労務・加工レート/為替/関税/物流費
- 数量階段/MOQ/リードタイム/代替可否/有効期間
これらを社内の様式やシステムの仕様に合わせて一覧表化しておけば、個人に依存しない見積プロセスを実現できます。
Step1:粗構成(Top-down)
見積BOM作成の最初のステップは、「粗構成の作成」です。
ここでは、製品を構成する部品ユニット・キット、消耗品を大まかに洗い出すことが目的です。
方法:ヒアリング or 仕様書 → 構成化
営業や設計へのヒアリング、または製品仕様書などをもとに、製品全体を業務ブロック図レベルで分解します。この段階では、10〜30の要素(部品群やサブユニット)を目安に構成が望ましいです。
粒度の原則:交換/購買単位まで
見積段階で詳細な工程情報まで入れてしまうと、作業工数が膨大になり、後の変更追従も困難になります。
構成の粒度は「交換できる単位」「購入できる単位」を上限とし、工程やルーティング情報はこの時点では含めません。
バリアント(オプション)管理:120%BOMや150% BOMの活用
構成に複数のオプションが存在する場合は、よく使用するオプションやバリエーションを含めた120%BOM、もしくは全バリエーションに加え、設計変更候補や未確定部品まで含めた150%見積BOMとして全パターンを包含した構成を作成します。
そこから、選択条件に応じて100%構成を抽出する仕組みにすることで、複数見積パターンにも柔軟に対応できます。
出力イメージ:粗構成リスト
- 部品群(ユニット・サブアセンブリ)
- キット品(複数部品の組み合わせ)
- 消耗品(パッキン、ケーブル類など)
この段階ではまだ正式な品番や原価は不要です。構成の骨格を固めることが目的となります。
Step2:標準化(Normalize & Map)
粗構成をもとに、次は社内データとの突合せ・正規化処理を行います。
このステップでは、曖昧な記述を排除し、見積で使える構成に整備していきます。
主な処理内容
- 同義語/社内略称の統一
例:「DCモーター」「直流モーター」→ 正式品番に統一 - Make or Buyの指定
内製か外注かを明確にし、原価算出方法に反映 - 代替可否/共通部品の指定
調達リスクや在庫活用に影響するため、属性として定義
キット化と展開抑制
- 頻出組合せを1品番化(キット化)
例:ねじ+スペーサ+ワッシャ → キット品A - ファントム品で階層展開を抑える
構成が深くなりすぎるのを防ぐため、展開不要の構成要素をファントム扱いに
品番未登録品の扱い
新作部品などがまだマスタ登録されていない場合は、
仮番(TMP-XXXX)を付与し、カテゴリや調達区分などの属性セットを付けて管理します。
この標準化処理を通じて、構成のブレや二重登録を防ぎ、後続の原価計算に必要なデータ精度を確保します。
Step3:見積原価計算(ロールアップ)
標準化された構成をもとに、部品ごとの原価を積み上げて見積価格を算出します。
このステップでは、数量や単価だけでなく、歩留まりや為替、間接費も加味することがポイントです。
各原価要素の計算ポイント
- 材料費
数量 × 単価 ÷ (1 – 歩留まり%) - 加工/外注費
セットアップ時間 × レート + 走行時間 × 数量 × レート
または、行単位で外注見積金額を入力 - 労務費・オーバーヘッド(OH)
(材料+加工) × OH%
※SGA(販管費)は見積書側で別計上することが多い - 物流費・関税・為替
重量または容積 × 物流単価
仕入通貨 × 為替レート
関税率は品目カテゴリごとに定義し、自動適用
合計原価と価格試算
製造原価 = 材料 + 加工 + 労務 + OH + 物流 + 関税
見積単価 = 製造原価 ÷ (1 - 目標粗利率)
出力形式:Qty Break・シナリオ別
- 数量階段ごとの単価(Qty Break)
- 標準/高速/コストダウンなどの見積シナリオ別価格
こうした構成ごとの原価を柔軟に出力できるようにしておくと、営業や購買からのフィードバックにも迅速に対応できます。
計算式例とチェックポイント
実務で見積原価を扱う際、どのような計算式を使うか/どんなミスが起きやすいかを把握しておくことが重要です。
よく使われるExcel計算式の例
- 拡張材料費
= ROUNDUP(Qty * UnitCost / (1 - Scrap%), 0) - 加工費
= SetupH * RateSetup + RunH * Qty * RateRun - 通貨換算
= SupplierCost * FX - 見積単価算出
= 原価合計 / (1 - GP%)
よくあるチェックポイント
- キット品と構成要素の二重計上
→ どちらか一方に統一し、IF式で排他処理 - NRE(治具・設計費)を構成に混在
→ 別建てで見積行を分離し、明示的に管理 - 端数処理や丸め
→ 数量・金額ともにルールを統一し、誤差が出ないよう制御 - 適用日の不一致
→ 為替・単価・レートの基準日を合わせる
これらのポイントを押さえることで、精度の高い・再現性のある原価計算が可能になります。
サンプルワーク【実践例】
ここでは、見積BOM作成の3ステップ(粗構成 → 標準化 → 原価計算)を、具体的な製品ケースで追体験できるように紹介します。
ケース:装置A
この装置は、標準ユニットに加えて、用途に応じた2種類のオプションを持つ構成です。
営業の見積段階で、顧客ニーズに応じて構成パターンを変える必要がある典型例です。
フロー:3ステップで構成〜原価算出
- 粗構成(ブロック図レベル)
装置全体を10〜20の機能ブロックに分け、オプションも含めた150%構成を作成します。 - 標準化マッピング表
各ブロックの構成要素を、社内品番にマッピング。代替可否、Make/Buy、カテゴリ情報などを付与し、仮品番も管理。 - 原価集計表の作成
品番ごとの数量や単価、レートをもとに、原価ロールアップを実施。
出力:3つの見積パターンを比較
- 標準構成:通常納期・標準単価での見積
- 大量構成:数量ブレーク適用によるコストメリット反映
- 短納期構成:緊急対応による加工費・物流費の加算を考慮
これらのパターンを並列表記することで、価格・粗利・納期別の最適案を顧客に提示することができます。
品質ゲートと承認フロー(RACI)【運用】
見積BOMは「作ったら終わり」ではなく、社内の各専門部門によるチェックと承認プロセスを経ることで、初めて信頼性のある構成として機能します。
RACIモデルによる役割分担
| 工程 | 主担当 | 関与部門 |
|---|---|---|
| 粗構成作成 | 営業/見積担当 | 設計、生産技術 |
| 技術妥当性チェック | 設計部門 | 営業、購買 |
| 生産性・加工性評価 | 生産技術 | 設計、購買 |
| 単価・調達性確認 | 購買部門 | 設計、生産技術 |
| 原価承認・登録 | 管理部門 | 営業、設計、購買 |
このように部門間でR(Responsible)/A(Accountable)/C(Consulted)/I(Informed)を整理することで、見積業務の属人化を防ぎ、ミスや抜け漏れを最小限に抑えられます。
品質チェック項目(自動検証推奨)
- 構成部品の網羅性
- レート・単価・為替情報の更新日
- 代替可否や共通部品の指定有無
- 有効期間(効果開始日/終了日)の整合性
Excelやシステム上で入力エラーや未確認項目をアラート表示させる仕組みを設けると、作業の信頼性が格段に高まります。
出力:見積書への自動転記
承認を通過したBOMからは以下の情報を見積書に自動反映させることで、手入力ミスを防止できます。
- 構成版数(Rev)
- 有効期限
- 前提条件(例:適用日・保証範囲など)
このように、品質ゲートと承認フローを設けることで、一貫性・再現性のある見積業務の基盤が整います。
よくある失敗と対策
見積BOMの作成・運用は、属人化や複雑化が起こりやすく、繰り返し発生するつまずきポイントがあります。
ここでは、現場でありがちな失敗と、その具体的な対処法をセットで紹介します。
❌ Problem 1:粒度が細かすぎて工数が膨張
構成を詳細にしすぎてしまい、見積ごとに手間と時間がかかる…
✅ Solution:交換/購買単位に粒度を制限
工程情報や設計レベルの分解は避け、「購入できるか」「交換対象か」で判断し、構成の粒度を一定に保ちます。
❌ Problem 2:キットと構成要素を両方計上
キット品とその構成部品を同時に入れてしまい、原価が二重になる…
✅ Solution:どちらか一方に統一(IF式で制御)
キットIDを条件に、キット優先/構成優先をIF関数で切り替えることで、重複計上を防止します。
❌ Problem 3:為替・物流費をざっくり入力
一律換算や概算入力により、実際の原価から大きく乖離してしまう…
✅ Solution:カテゴリ別の係数テーブルを用意
重量・容積・仕入通貨などに応じた係数をあらかじめ設定し、自動適用する仕組みにすると精度が向上します。
❌ Problem 4:既存品の原価が古いまま
マスタ登録されている品番の標準原価が更新されず、誤った見積に…
✅ Solution:更新日フラグで警告表示
原価やレートに「最終更新日」を紐づけ、古い場合はエラーや色付けで視認性を高めます。
❌ Problem 5:NRE(治具・開発費)が本体に混在
イレギュラー費用が構成に混ざってしまい、繰り返し見積で混乱が生じる…
✅ Solution:NREは別見積行に分離
構成とは別に「NRE専用行/シート」を設け、明示的に管理することで、見積の明快性と再利用性が高まります。
❌ Problem 6:代替可否や適用日が曖昧
部品の選択可否や有効期間が不明確で、見積の条件がバラつく…
✅ Solution:属性必須化+承認ゲートで管理
品番や構成要素に「代替可否」「有効開始日/終了日」を必須入力とし、品質ゲートでチェックすることで一貫性を確保します。
これらの失敗は、どれも「最初は見逃されやすいが、後で大きな影響を及ぼす」ものばかりです。
事前に対策ルールを仕込んでおくことで、手戻りや原価誤差のリスクを大幅に減らすことができます。
KPIと改善ループ
見積BOMの運用効果を可視化し、継続的な改善につなげるには、適切なKPI(評価指標)の設定と分析が欠かせません。
主な評価指標(KPI)
- 原価誤差:見積時点の原価と実績原価の乖離(%)
- 一次回答TAT:初回見積の提出までに要したリードタイム
- 再見積率:再提出が必要となった割合
- 受注勝率:提出見積に対する受注件数の比率
- 粗利乖離:想定粗利と実績粗利の差異
これらのKPIは、営業・原価・購買など複数部門で共有することで、全体最適に向けた改善アクションの起点となります。
ダッシュボードの例:誤差の寄与分解
- 材料費の変動要因(単価/歩留まり)
- 労務・加工レートの更新有無
- 為替の適用日・レートのずれ
- 物流・関税コストの見積時と実績の差
こうした誤差要因の寄与を分解・可視化する仕組みを導入すれば、「どこを見直すべきか」「何が繰り返しのミスか」が明確になり、次回以降の見積精度向上に直結します。
システム連携(任意)
見積BOMの構築や活用を、表計算や属人的な運用だけにとどめず、他の業務システムと連携させることで精度と再現性をさらに高めることが可能です。
代表的な連携システム
- PLM(製品ライフサイクル管理)
設計BOMとのデータ整合性や図面管理との連携 - ERP(基幹業務システム)
品番、標準原価、為替、通貨、調達情報との整合 - CPQ(構成・価格自動化)
営業・提案プロセスにおける構成選定や価格算出の自動化
連携すべき主な項目
- 品番/通貨/為替/標準原価
- オプションID(構成ルール)
- 効果開始日・終了日(有効期間)
- BOMの版数(Rev)
- 見積前提条件(保証範囲、数量階段など)
こうしたデータをシステム間で連携させることで、転記ミスや更新漏れを防ぎつつ、チーム間で一貫性のある見積運用が可能になります。
まとめ
ここまで、見積BOMを構築・活用するための一連の流れを解説してきました。
見積のスピードと精度を両立するためには、次の3ステップが鍵となります。
見積BOMの3ステップ再掲
- 粗構成:仕様書やヒアリングから構成要素をブロック単位で洗い出す
- 標準化:社内品番・カテゴリ・属性を用いて構成を正規化
- 原価計算:材料費・加工費・間接費を積み上げて見積価格を算出
これらのプロセスを整備することで、属人化を防ぎ、見積の再現性・透明性・スピードを飛躍的に向上させることができます。