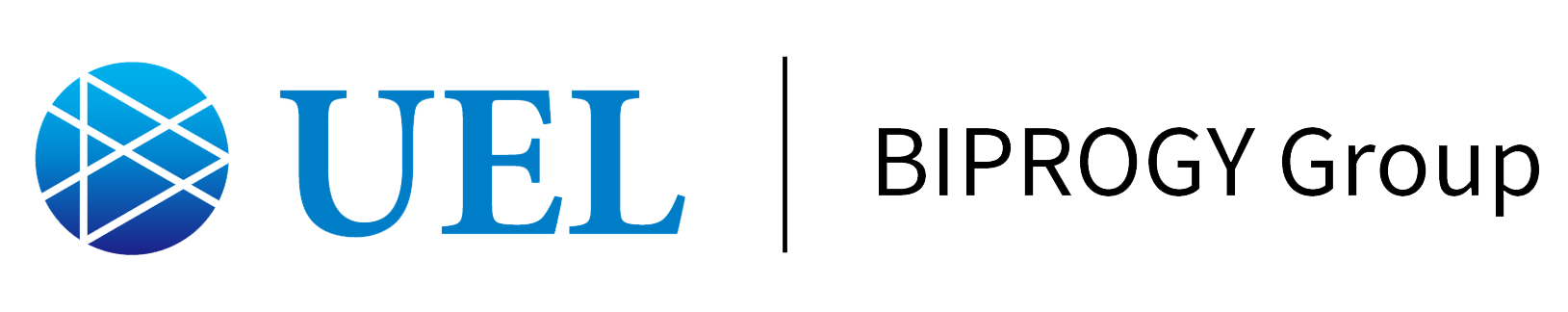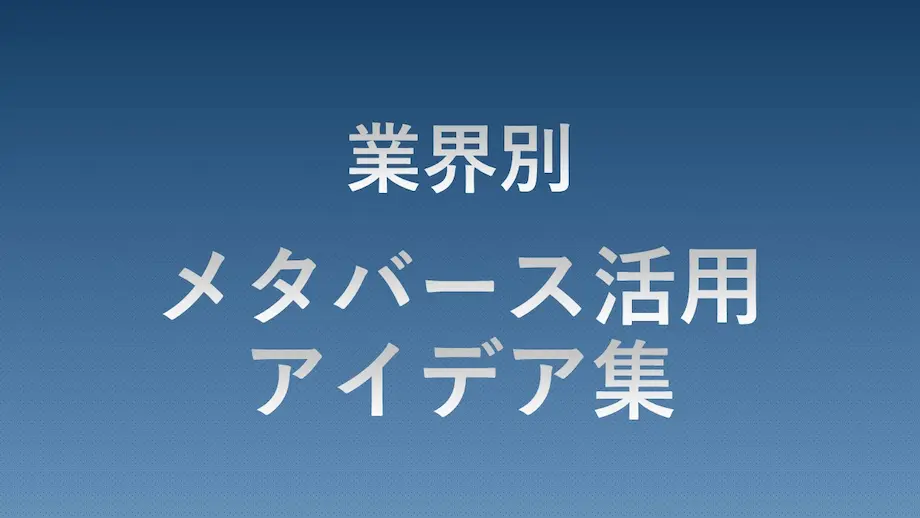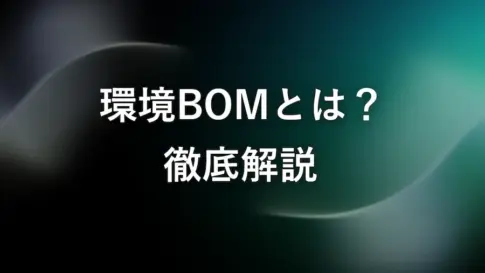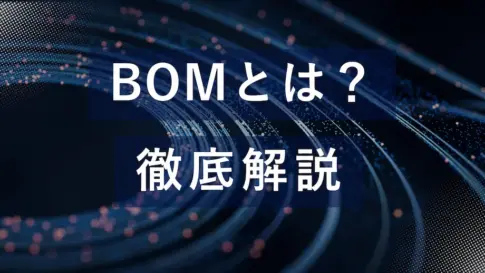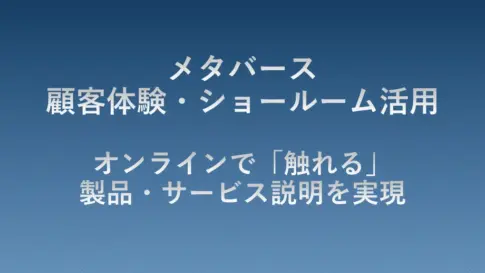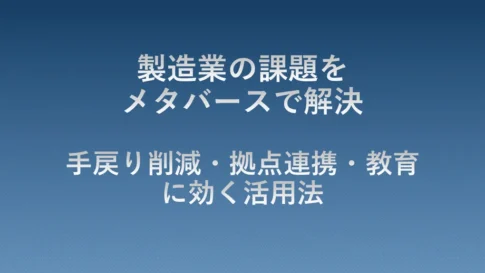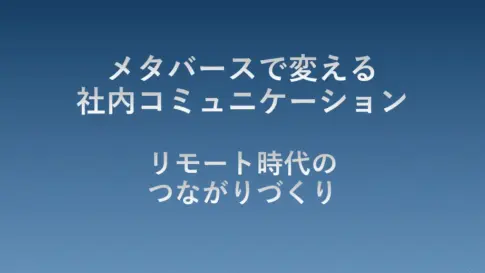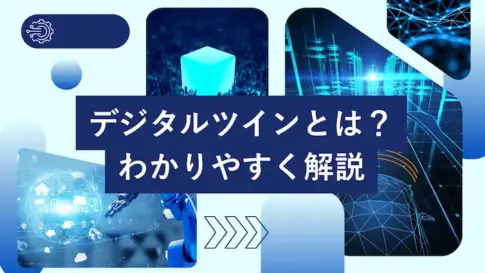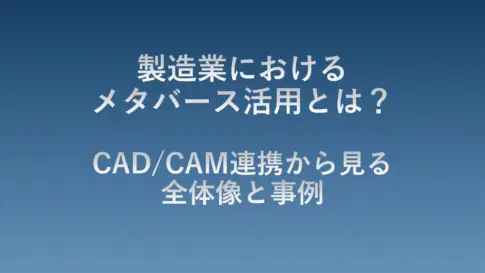メタバースとは、離れた場所にいる相手とも同じ場にいるように感じながら、交流・学習・検討ができる仮想空間です。仮想空間上で人・モノ・情報をつなぎ、画面越しでも「その場にいる感覚」で体験を共有できます。
メタバースは、VRゴーグルだけが前提ではありません。PCやスマホのブラウザから参加できる共有空間として、離れていても同じものを見て、同じタイミングで体験を共有できるのが強みです。まずはメタバース活用の事例を探したい方や、真似できるヒントを得たい方に向けて、誰でも試しやすく、再現性の高い活用アイデアを業界別に整理しました。本記事では、業界別に見るメタバースの活用案からよくある質問まで紹介します。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の企業・環境・状況への適用や効果を保証するものではありません。内容の利用は読者ご自身の判断と責任にてお願いいたします。参考としてご活用ください。
あわせて読みたい:メタバースとは?|メタバースの全体像を徹底解説

監修・執筆:UEL株式会社編集部
UEL株式会社のTechデザイン企画部と現場に精通した社内有識者が監修しています。
目次
小売業(店舗・EC)
アパレルショップやインテリアショップなどの小売店では、顧客は「見て・試して・相談して」から購入に至ります。この体験をオンラインのメタバース空間で再現することで、商品理解の深化やイベント集客、EC導線の強化等が実現できます。メタバースを上手く活用することで、売上や来客促進の効果が期待できます。例えば、新作発表を仮想会場で実施し、来場者にクーポンや限定閲覧を提供してECへ誘導することで、店舗・EC・SNSと一体化した導線設計により、来場から購入までの落ちを減らすことが期待できます。
ユースケース
- 接客 —アバターによるサイズ相談、在庫案内、コーデ提案
- 試着体験— カラー変更、素材感の確認、比較表示
- 商品体験 — 機能デモ、カスタマイズの即時プレビュー
- イベント — 新作発表会、限定販売、コミュニティ施策
導入ステップ
- 目的とKPIの設定 — 来場・閲覧・購入・再訪など
- PoC設計 — 限定SKU・短期イベント
- 本番化 — EC・在庫・会員と連携/運用体制の確立
- 効果測定 — 来場→体験→カート→購入の可視化
注意点
- 著作権 — 素材の権利確認(画像・3D・BGM・フォント)
- 個人情報 — 取得目的・保存期間・第三者提供の明示、会員ID連携時の最小化
- 炎上対策 — 行動ルールと通報動線の明確化
医療
医療では、遠隔カンファレンスやトレーニング/研修でメタバースの効果が期待できます。現場で何度も実施しにくい作業を安全な仮想空間で繰り返し体験できるため、知識・技能の定着やチーム内の共通理解を高めやすくなります。
ユースケース
- 術前シミュレーション — 3Dモデルで術式や段取りを事前検証し、リスクや注意点を共有
- 患者教育 — 治療手順や術後の注意点を視覚的に説明し、納得感を高める
- 職員研修 — 標準手順の反復学習や、緊急時対応を安全に模擬演習
合意形成が得やすい教育・研修領域から小さく開始すると、導入障壁を下げられます。既存教材の再利用や短時間の演習シナリオで効果を確認し、段階的に対象を拡大します。
注意点
- 費用要素 ー3D教材制作、アカウント・権限管理、配信・運用環境
- 技術的ハードル ー セキュアな通信、認証方式、閲覧端末の整備
- 法務・情報管理 ー 識別可能情報の扱い、アクセス権限の分離、ログ管理
- コンプライアンス ー 運用規程に明文化し、関係者で遵守を徹底
目的(例:研修の質向上、合意形成の迅速化)を明確にし、短いサイクルで検証→改善を繰り返すことが成功の近道です。
不動産
物件探しでは、間取りや採光、周辺環境などを体感して判断したい一方、現地内見には時間と労力がかかります。状況によっては現地に足を運ぶことが物理的に難しいケースも考えられるでしょう。メタバースを使えば、遠方にいてもバーチャル内見で確認でき、比較検討のスピードを上げられます。また、気に入る物件が見つかるまで何度でも内見できます。結果として、内見〜成約までのリードタイム短縮や、ミスマッチの減少が期待できます。
ユースケース
- 新築販売 ー 完成前でも、完成後の暮らし方や眺望・採光を3Dで体験
- 賃貸内見 ー 家具配置・動線・収納量・日当たりを具体的に確認
- 再開発PR ー 街並みの将来像を共有し、関係者間の合意形成を支援
導入ステップ
- 目的とKPIの設定 ー 来場(閲覧)数、内見予約率、商談率、成約率、キャンセル率など
- PoC設計 ー 対象物件を限定し、操作性や伝わり方を検証
- 効果測定と改善 ー 閲覧 → 内見予約 → 商談 → 契約の各段階で離脱要因を特定し、導線・説明・演出を改善
注意点
- コスト構成の把握 ー 物件・街並みの3D制作、配信・表示環境、更新運用の体制
- 権利・掲載ルール ー 図面や素材の権利確認、撮影・掲載の可否、周辺画像の取り扱いを明確化
- 情報の正確性 ー 実物との差異(寸法・色味・眺望など)は注記し、誤解を避ける
現地案内を完全に置き換えるのではなく、事前理解を深める第一段階の内見として活用することで、来場の質と成約までのスピードを同時に高められます。
製造業
製造業でのメタバース活用は、「3Dで共有 → 同時に合意 → 現場に効く改善」を素早く回すための仕組みづくりが核です。小さなPoCで効果を数値で確認し、テンプレ化と再利用で横展開すれば、設計・製造・品質・保守の各領域で、手戻り削減・教育効率化・一次解決率向上が期待できます。
ユースケース
- 試作削減 ー 仮想試作で組立手順・交換性・工具クリアランスを事前検証し、実機試作を最小化
- 共同設計レビュー ー 3Dモデルを同時閲覧+注釈/寸法確認。図面では見落としやすい干渉・組付け性を早期に可視化
- ライン立上げシミュレーション ー 作業動線・サイクルタイム・人と設備の干渉を仮想空間で確認し、立上げリスクを低減
- 安全教育 ー 挟まれ・巻き込まれ・高所などの危険源を安全に模擬体験し、注意点を定着
導入のポイント
- 目的とKPIを先に固める ー リードタイム短縮/不良・手戻り削減/教育コスト削減/保守の一次解決率向上など
- 小さく始めて、勝ち筋を確認 ー 1ライン/1工程/1設備など“狭く深い”範囲で、3〜8週間の検証を実施
- テンプレ化 ー 手順書・教育シナリオ・レビュー進行をテンプレート化し、再現性と速度を確保
- コンテンツ再利用 ー 共通機構や類似工程を部品化して横展開し、制作負荷を抑制
まずは小規模PoCで「どこに効くか」を数値で確認し、成功パターンを標準化。その後、対象工程や拠点へ段階的に広げるのが最短ルートです。
エンターテイメント・観光
エンタメや地域PRでは、「参加したくなる仕掛け」づくりが成果を左右します。メタバースはライブ・展示・交流を一体化し、来場(参加)から購買・寄付・来訪予約までの動線をスムーズにします。
ユースケース
- エンタメ ー ライブ視聴、限定アイテム配布、ファン交流、記念撮影
- 観光 ー 名所の3D体験、文化・食の紹介、現地イベントへの送客
- 地域創生 ー 地域ならではの名所ツアーや伝統行事の体験型展示
成功のコツ
- 期間限定×地域連動の企画 ー 注目を集め、来場 → 購入・寄付・来訪予約へ自然に誘導
- ファン化の仕掛け ー 人との交流(主催・出演者・参加者)と、ここでしか体験できない演出で愛着を醸成
- 分かりやすい行き先 ー 配信ページや物販・予約のリンクを明確に、会場内の案内を統一
注意点
- 権利確認 ー 音源・キャラクター・ロゴ・画像等の利用条件を事前に精査
- ルール策定 ー コミュニティガイドライン、通報・対応フロー、モデレーション体制を明文化
実施チェックリスト
□ 目的とKPI:参加数/視聴時間/購入・寄付率/予約率
□ 体験設計:ライブ・展示・交流の導線と役割を定義
□ 参加動機:限定アイテム、抽選、記念フォトなどの来場理由を用意
□ 送客設計:購入・寄付・予約ボタンの位置と案内文を統一
□ ガバナンス:権利・ルール・通報フォーム・対応担当を事前に確定
ポイントは「来場理由をつくる → 交流で熱量を高める → 次の行動へ最短で導く」。この基本を守れば、オンラインの盛り上がりを、確かな成果へ結びつけられます。
社内コミュニケーション
メタバースは、社内の集会・研修・交流・採用などを一体感と双方向性で底上げします。リモートや拠点分散で減りがちな“偶発的なつながり”も、気軽に集まれる仮想空間を用意することで、相談の初動が軽くなり、称賛・歓迎・雑談が自然に生まれます。
ユースケース
- 立ち話スペース ー 短時間の相談・雑談のための常設エリア
- ワークショップ ー 共同作業・アイデア創出・発表までを一気通貫で実施
- 採用活動 ー 社内ツアー、文化・歴史・制度を歩いて学べるインタラクティブ展示
- 社員研修 ー ロール別レクチャーやOJT前の事前学習に活用
注意点
- 目的が曖昧 ー 事前に何を達成したいかと測定指標を共有
- 操作で混乱 ー 事前チュートリアルと当日のヘルプデスクを用意
- 放置で荒れる ー 進行役・モデレーションの役割、通報フローを明確化
実施チェックリスト
□ 目的とKPIが合意済み
□ ルールと権限(録画・ログ・公開範囲)が明文化
□ 進行台本・タイムライン・役割分担が準備済み
□ 初回参加者向けの操作ガイドとFAQが用意済み
□ 振り返りアンケートと改善サイクルを回す体制がある
重要なのは、「集まる理由を作る → 双方向で熱量を高める → 次の行動につなぐ」流れを毎回設計すること。小さく試して改善を重ねるほど、社内のつながりと成果が育ちます。
よくある質問(FAQ)
特別な機材は必要ですか?
PCやスマートフォンで始められます。
ARやVRなどの没入型機器は任意です。まずはお手持ちの端末で小規模にスタートしていただくと、費用を抑えられます。
VR・ARの長時間の利用は大丈夫ですか?
個人差があります。
VRやARでメタバースを体験する際は、定期的に休憩を取るようにしましょう。メタバースを製作する際は、表示・音量・姿勢を調整する前提で設計するのがベターです。
何から着手すべきですか?
メタバース活用の目的を明確にしましょう。
目的を一つに絞り、試行→アンケート→改善のサイクルを回すのが近道です。成功パターンが見えたら対象を段階的に拡大していきましょう。
成果はどのように測りますか?
参加率・離脱率・満足度の三点に、目的別KPI(合意日数、予約率、発言率など)を加え、前回比で判断します。
まとめ
本記事では、業界別にメタバースのユースケースや導入のポイント、注意点等を整理して紹介しました。まずは小さく試し、KPIで効果を測り、成功パターンをテンプレ化して横展開するのがメタバース活用の近道です。既存資産の再利用と、セキュリティ・権利配慮を徹底し、体験価値と業務効率の両立を実現しましょう。