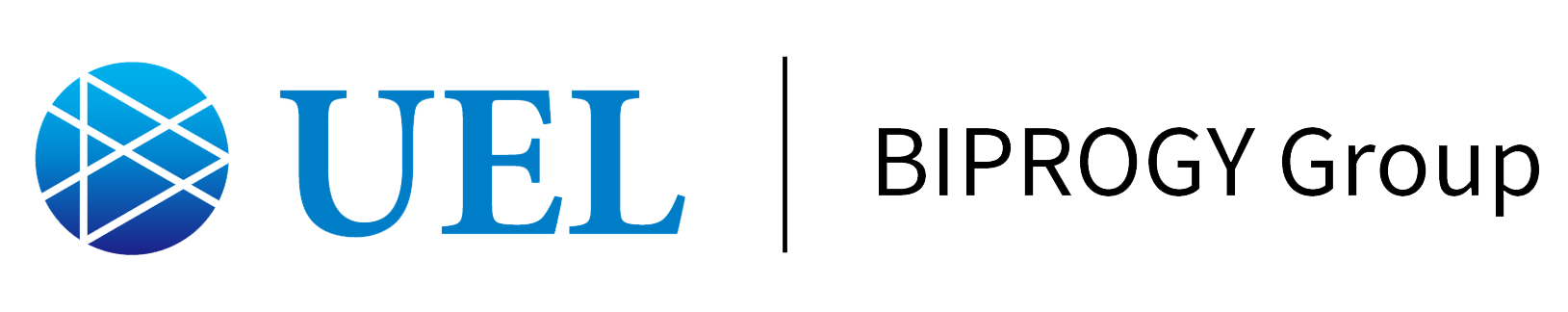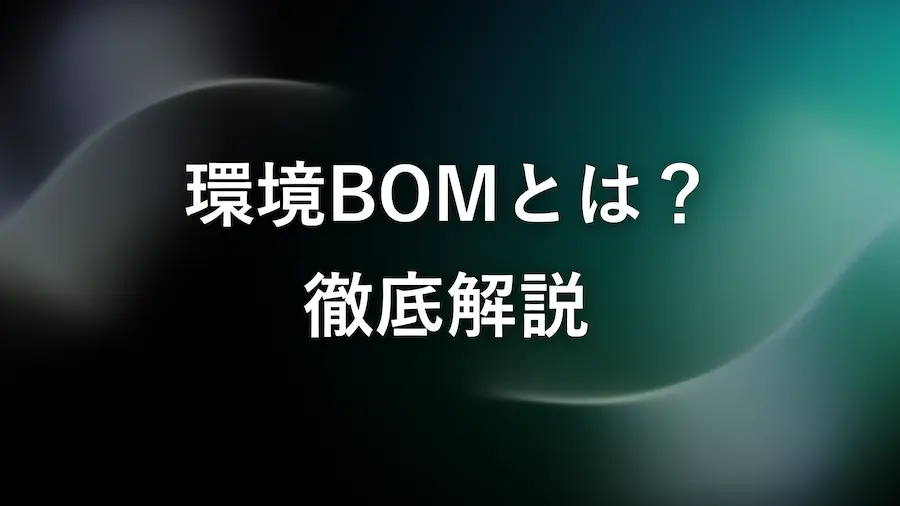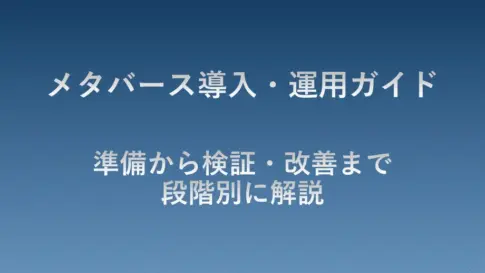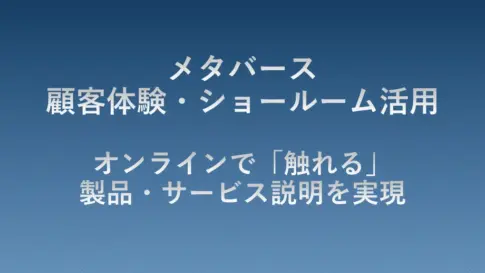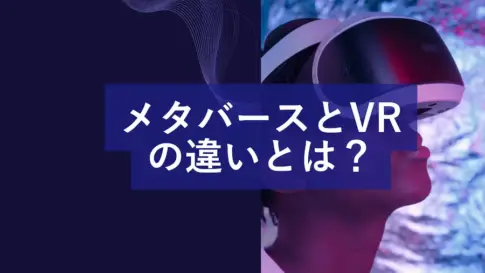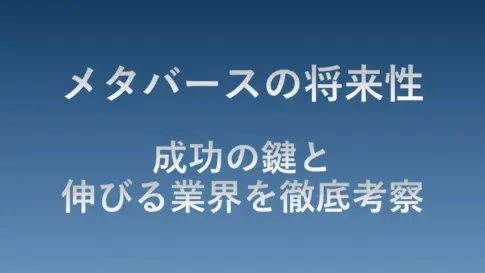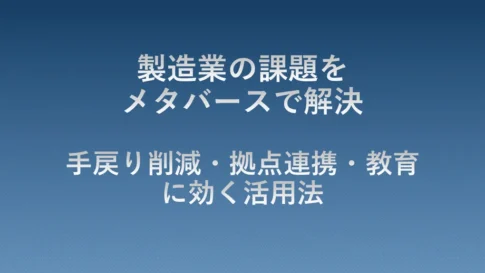製品の設計や調達の現場では、環境法規制への対応がこれまで以上に重要になっています。
特にRoHS指令やREACH規則といった化学物質関連の規制は、国際的に適用範囲が広がり、企業は製品に含まれる化学物質の情報を正確に把握・管理することが求められています。
その際によく使われるのが「環境BOM」という言葉です。
ただし、これは正式な法令用語ではなく、一般的には製品に含有する環境負荷物質の情報を管理するための部品表(BOM: Bill of Materials)を指す便宜的な表現です。
本記事では、この「環境BOM」という考え方をもとに、
- どのような情報を管理するものか
- RoHSやREACHとどのように関係するのか
- 実務でどのように活用されているのかといったポイントを、できるだけわかりやすく整理します。
また、chemSHERPAやIMDSといった業界標準スキームにも触れながら、
日々の業務で環境情報を扱う方に向けて、中立的な立場で基礎から実務までを紹介します。
専門用語が多い分野ですが、初めての方でも読み進めやすい内容を目指しています。
本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の法的判断や適合可否を保証するものではありません。実際の対応や判断を行う際は、最新の法令・顧客要求・専門機関の情報をご確認ください。または、弊社の有償サービスにお問い合わせください。
あわせて読みたい:BOMとは?|定義・種類・作成手順・管理ベストプラクティスまで徹底解説

監修・執筆:UEL株式会社編集部
UEL株式会社のTechデザイン企画部と現場に精通した社内有識者が監修しています。
目次
本記事における「環境BOM」の定義と範囲
「環境BOM」は正式用語ではない
「環境BOM(かんきょうボム)」という言葉は、現時点では法令や国際規格などで正式に定義されている用語ではありません。
一般的には、製品や部品に含まれる環境負荷物質の情報を管理するために使われる部品表(BOM:Bill of Materials)を、わかりやすく説明する際の便宜的な呼称として使われています。
この言葉は特定の業界標準に基づくものではなく、各企業や組織が社内の運用や説明の中で使い始めたものと考えられます。そのため、「環境BOM」という表現の意味や適用範囲は、企業や業界によって少しずつ異なる場合があります。
本記事の限定的定義:製品に含有する環境負荷物質情報の管理を目的としたBOM
本記事では、「環境BOM」を製品に含まれる環境負荷物質の情報を整理・管理するための部品表として扱います。
ここで対象とする環境負荷物質とは、主にRoHS指令やREACH規則などで規制・制限の対象となる化学物質を指します。
この定義では、環境BOMの目的を以下のように位置づけています。
- 製品中に含まれる化学物質の有無や濃度を把握すること
- 法令や顧客要求に基づく適合状況を確認できるようにすること
こうした情報は、製品設計、調達、品質管理、出荷判定などの各プロセスで利用され、環境法規制への対応やデータ提出の基礎となります。
脱炭素・リサイクル等の広義情報は対象外
近年では、化学物質情報だけでなく、カーボンフットプリント(CO₂排出量)やリサイクル材の使用率など、より広い意味での環境情報を管理する動きも広がっています。
これらは将来的に「環境BOM」に含まれていく可能性がありますが、本記事では対象範囲を限定し、化学物質関連の情報管理に焦点を当てています。
脱炭素やリサイクル情報などは、別の仕組みや報告体系で扱われることが多く、本記事では取り上げません。化学物質管理の領域に焦点を絞ることで、実務上の理解と対応をより明確に整理します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の法的判断や適合可否を示すものではありません。実際の運用や判断を行う際は、最新の法令や顧客要求、各国のガイドラインなどを必ずご確認ください。
環境BOMの基本
通常BOMとの違い
一般的なBOM(部品表:Bill of Materials)は、製品を構成する部品や材料、数量などを一覧化した設計・製造の基礎情報です。
これに対して「環境BOM」は、同じ構成情報をベースにしながら、環境負荷物質に関する情報を追加して管理する点に特徴があります。
通常のBOMが「何を、どれだけ使うか」を示す設計上の情報であるのに対し、環境BOMは「その部品や材料に、どのような化学物質が含まれているか」を把握するための情報を含みます。
RoHS指令やREACH規則などでは、特定の化学物質の含有や使用量が制限されています。
そのため、製品がこれらの規制に適合しているかを確認するには、部品レベルでの化学物質情報が必要になります。
環境BOMは、こうした情報を整理・蓄積し、製品全体の適合性を確認するための基盤として利用されます。
また、通常BOMと環境BOMを連携させることで、設計変更や部品代替を行う際にも、環境面への影響を効率的に確認できるようになります。
なぜ今必要か
環境BOMの整備が求められるようになった背景には、法規制の拡大と、サプライチェーン全体での情報透明性の重視があります。
欧州連合のRoHSやREACHをはじめ、アジアや北米でも同様の規制が整備され、適用範囲が年々広がっています。
さらに、取引先や完成品メーカーからも、化学物質の含有情報をデータとして提出することが求められるケースが増えています。
このような状況では、個別の資料やメールで情報を管理する方法では限界があり、データの一元管理が重要になります。
環境BOMは、これらの情報を体系的にまとめ、継続的に更新できる仕組みとして活用されています。
整備しておくことで、法改正や顧客要求の変更があった際にも、迅速かつ柔軟に対応しやすくなります。
活用場面(設計/購買/出荷判定/監査)
環境BOMは、設計から出荷、さらには監査対応まで、製品ライフサイクルのさまざまな段階で利用されます。
設計段階では、新しい部品や材料を採用する際に、規制物質が含まれていないかを確認する判断材料として活用されます。
初期段階で化学物質情報を把握しておくことで、後工程での部品差し替えや出荷延期といったリスクを減らすことができます。
購買部門では、サプライヤからの環境情報の収集や確認に利用されます。
環境BOMをもとに、どの部品の情報が未回収か、どのサプライヤのデータが古いかを把握しやすくなります。
出荷判定の際には、製品がRoHSやREACHなどの環境法規制に適合しているかを確認する根拠データとして使われます。
顧客への回答や証明書類の作成にも、このデータが基礎となる場合があります。
また、監査や社内品質管理の場面でも、環境BOMが整備されていれば、調査実態や証跡、更新履歴をすぐに確認でき、対応のスピードや信頼性が高まります。
このように環境BOMは、単なる化学物質情報の一覧ではなく、製品の環境適合を支える情報基盤として活用されています。
適用規制と業界スキームの全体像
主な環境法規制(RoHS/REACH ほか)
製品に含まれる化学物質を管理するうえで、国際的に重要とされているのがRoHS指令とREACH規則です。
これらはいずれも、製品の安全性や環境への影響を低減することを目的としていますが、対象範囲や運用方法に違いがあります。
RoHS指令は、主に電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するための規制です。
鉛やカドミウム、水銀、六価クロムなどが対象で、濃度の上限値が均質材料レベルで定められています。
この指令はEU域内での販売を目的とする製品に適用されますが、各国でも類似の法令(例:中国RoHSなど)が整備されています。
適用除外と言って、特定の使用方法には特例が認められるケースがありますが、この特例には期限が定められているため、正しい期限管理も必要になります。
REACH規則は、より広い範囲で化学物質を管理する制度です。化学物質の登録、評価、認可、制限を体系的に行うもので、製品に含まれる高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)の情報開示も求められます。
SVHCが一定濃度(0.1wt%)を超える場合は、EUのSCIPデータベースへの届出が必要となるケースもあります。
このほか、アメリカのProposition 65(カリフォルニア州法)やPFAS(有機フッ素化合物)規制、POPs規則(残留性有機汚染物質)、韓国や中国の独自規制など、国・地域ごとに異なる制度が存在します。
環境BOMでは、これら複数の法規制に共通する化学物質情報を整理し、適合性を確認する基礎として活用されます。
業界標準スキームの概要
環境法規制に対応するためには、単に社内でデータを管理するだけでなく、取引先間で情報を正確に共有する仕組みが必要になります。
そのため、業界ごとに共通のデータフォーマットや報告スキームが整備されています。
chemSHERPA(ケムシェルパ)は、日本国内を中心に広く利用されている化学物質情報伝達スキームです。
製造業や電子部品業界などで標準的に使われており、RoHSやREACHに関する物質データを共通形式でやり取りできるよう設計されています。
製品レベルの情報を扱う「chemSHERPA-AI」と、部品や材料の情報を扱う「chemSHERPA-CI」があり、データの統一性と再利用性が重視されています。
IMDS(International Material Data System)は、自動車業界向けのグローバル標準システムです。
部品・材料・化学物質を階層構造で登録し、自動車メーカーとサプライヤ間で情報を共有します。
IMDSは、GADSL(Global Automotive Declarable Substance List)と連携しており、各国の法規制に基づく物質管理を支える仕組みとして運用されています。
IPC-1752AやBOMcheckは、主に欧米企業や電子部品サプライチェーンで利用されるデータ交換フォーマットです。
IPC-1752Aは電子機器業界向けの環境情報伝達標準で、RoHSやREACHを含む複数の規制に対応した形式を提供します。
BOMcheckはオンラインベースのデータ共有プラットフォームとして、多国籍企業が取引先との化学物質情報のやり取りに用いています。なお、サプライヤはBOMcheckで物質情報を報告するだけでも利用料の負担が課せられます。
なお、JAMP AISおよびMSDSplusは、かつて日本国内で広く利用されていた化学物質情報伝達スキームですが、2015年以降はchemSHERPAへの移行が進められています。現在ではchemSHERPAが国内の標準スキームとして位置づけられるケースが一般的です。
これらのスキームは、どれか一つを選べばよいというものではなく、製品分野や取引先の要求に応じて使い分けられます。環境BOMを構築する際は、こうした共通スキームを意識しながら、データの互換性や信頼性を確保することが重要とされています。
環境BOMに含めるべきデータ項目
環境BOMは、単に部品の一覧を示すだけではなく、環境法規制への適合を確認するための情報を体系的に整理したデータ群です。
設計、調達、品質保証、監査などのさまざまな部門で共通して利用できるよう、構造化されたデータとして整備されることが望まれます。
ここでは、環境BOMに含める主要な項目を紹介します。
階層構造
環境BOMは、製品全体から最小構成単位である均質材料までを階層的に整理します。
一般的な構成は次のようになります。
- 製品(最上位)
- 部品またはユニット
- 材料(均質材料=機械的に分離できない最小単位)
この階層構造によって、特定の部品や材料に含まれる化学物質を追跡しやすくなります。
たとえば、製品全体では適合しているように見えても、個別の部品で規制物質が閾値を超える可能性があるため、階層ごとの情報整理が欠かせません。
物質情報(名称・CAS・濃度・質量・使用用途)
環境BOMの中心となるのが、部品や材料に含まれる化学物質の情報です。
一般的に以下の項目が含まれます。
- 化学物質名
- CAS番号
- 含有濃度(%やppmなど)
- 質量(部品または均質材料中の含有量)
- 使用用途(認められた用途での利用かどうか。官報公示番号と紐づけ)
これらの情報は、RoHSやREACHなどの法規制対象物質を特定し、適合状況を判断するために利用されます。
CAS番号のような国際的に共通の識別情報を用いることで、取引先や海外拠点とのデータ共有も容易になります。
判定情報(RoHS適合/REACH SVHC)
化学物質情報を基に、各法規制に対する適合判定を行う項目も重要です。
たとえば次のような情報が整理されます。
- RoHS指令における制限物質の有無と閾値超過判定、及び適用除外と有効期限の確認。
- REACH規則におけるSVHC(高懸念物質)の該当有無
- SCIP届出が必要な場合の該当情報
- 各国または顧客独自リストへの該当可否
これらの判定結果は、製品出荷時の環境適合証明や顧客への報告書作成の根拠として利用されます。
法規制は定期的に更新されるため、判定情報も随時見直しが必要になります。
メタデータ(部番・サプライヤ等)
環境BOMでは、化学物質以外の管理情報(メタデータ)も欠かせません。
これにより、データの真正性や追跡性を確保できます。
主な項目には次のようなものがあります。
- 部品番号、部品名称
- サプライヤ情報(会社名、部署名、連絡先)
- 調査有無/完了日
- 調査様式とバージョン
これらの情報を付与しておくことで、将来的な更新や監査対応の際に、どの時点・どの情報源に基づいてデータが作成されたかを明確にできます。
証拠書類とトレーサビリティ
環境BOMの信頼性を支えるのが、証拠書類とトレーサビリティの確保です。
部品や材料の含有情報は、サプライヤからの証明書や分析データに基づいて登録されるケースが多く、これらの裏付け資料を管理する仕組みが必要になります。
代表的な証拠資料には、次のようなものがあります。
- DoC(Declaration of Conformity:適合宣言書)
- 不使用報告書(各法令での禁止対象物質の不使用を宣言する書類)
- 試験報告書や分析証明書
これらをBOMデータと紐づけることで、監査や顧客要求に対して根拠を提示しやすくなります。
また、部品変更や新規採用時には、証拠書類を更新し、古いデータを誤って使用しないように管理することも重要です。
環境BOMは、単なる一覧表ではなく、正確なデータと裏付け資料を組み合わせて運用される情報基盤です。
構造、物質データ、判定情報、メタデータ、証拠書類を一体的に扱うことで、規制対応の効率と信頼性を高めることができます。
ゼロから始める環境BOMの作り方
環境BOMを新たに整備する場合、最初はどの情報をどの順序で扱うべきか迷うことが多いです。
ここでは、基本的な進め方を段階ごとに整理し、一般的な実務フローの流れをわかりやすく説明します。
スコープ定義
最初のステップは、対象とする範囲を明確にすることです。
どの製品や部品を対象にするのか、どの規制(RoHS、REACHなど)に対応するのかを整理します。
また、法規制ごとに閾値や適用条件が異なるため、社内で共通の判断基準を持っておくことが大切です。
スコープを明確にすることで、データ収集時の抜け漏れや優先度の混乱を防ぎやすくなります。
複数部門で関わる場合は、関係者間で認識を共有しておくことが重要です。
データ収集
次に行うのが、必要な化学物質情報の収集です。
サプライヤや社内の設計・調達部門など、複数の情報源からデータを集める必要があります。
主な収集方法には、次のようなものがあります。
- サプライヤへの環境情報依頼(chemSHERPA形式など)
- SDS(安全データシート)や試験報告書の入手
- 材料仕様書や図面からの情報抽出
- 必要に応じた社内試験の実施
この段階では、情報の精度よりも、まずどの部品のデータがそろっているかを把握することが重要です。
未入手のデータについては、リスト化してフォローアップできるようにしておきます。
データ整形
収集した情報は、提供元や形式が異なることが多く、そのままでは集計や判定に使いにくい場合があります。
そこで、単位・名称・コードなどを統一し、環境BOMとして扱いやすい形に整えます。
代表的な作業には次のようなものがあります。
- 均質材料レベルへの情報分解
- 部品コードやサプライヤ名の整理
- 欠損データや重複登録の確認
- 化学物質の名寄せ(同一CAS Noで物質名称が異なる場合の表現の統一)
データ整形は環境BOMの基礎となる作業であり、この段階の精度が後の工程に大きく影響します。
スキーム変換(chemSHERPA/IMDS)
整形したデータは、取引先や業界の要求に応じて提出フォーマットに変換します。
代表的なスキームには次のものがあります。
- chemSHERPA:電機・電子業界を中心に普及している国内標準スキーム
- IMDS:自動車業界向けの国際標準システム
スキーム変換では、入力ルールや検証機能を利用することで、データの不備や形式エラーを減らせます。
自動変換ツールを活用する場合も、最終的な確認は担当者が目視で行うことが望ましいです。
妥当性確認
登録されたデータが正しいかどうかを確認する工程です。RoHSやREACHなど、対象となる法規制の閾値を超えていないかをチェックします。また、入力漏れやデータの不整合がないかも確認します。
サプライヤからの情報をそのまま登録するのではなく、可能であれば内部監査や分析データとの照合を行い、信頼性を確保します。
承認と版管理
妥当性を確認した後は、社内で承認し、正式なデータとして登録します。
環境BOMは一度作成して終わりではなく、部品変更や法改正などのタイミングで更新が必要になります。
そのため、改訂履歴を管理し、いつ・誰が・どの理由で修正したかを記録しておくことが重要です。
承認プロセスは、設計、品質、環境管理など複数部門での確認を経て行うケースが多く見られます。
提出・届出
最終的に整備した環境BOMは、取引先や当局への提出・届出に使用します。
提出先や国によってフォーマットや提出方法が異なるため、事前に要件を確認しておく必要があります。
主な用途としては、以下が挙げられます。
- chemSHERPAデータの提出(電子機器分野など)
- IMDS登録(自動車分野)
- REACH規則に基づくSCIP届出(EU域内向け製品)
届出後も、法改正や部品変更により内容が変わる場合があります。
そのため、提出履歴と更新記録を一元管理しておくと、再提出や監査対応がスムーズに行えます。
環境BOMの構築は、単なる情報整理ではなく、製品の信頼性やコンプライアンス体制を支える基盤づくりにつながります。
最初から完璧を目指すよりも、正確で更新しやすい仕組みを整えることが継続的な運用の鍵になります。
実務で役立つノウハウ
環境BOMの運用は、単にデータを作成・提出するだけではなく、日々の業務の中で確実に運用・改善していくことが求められます。
ここでは、実務担当者が知っておくと役立つポイントを、現場での課題や対応の流れに沿って紹介します。
均質材料の切り分け
環境BOMを作成する上で最も重要な基本が「均質材料」の正しい切り分けです。
均質材料とは、化学的または機械的に分離できない最小単位を指します。
たとえば、メッキされたネジは「鉄」と「メッキ層(金属皮膜)」に分けて扱う必要があります。
切り分けの粒度が粗すぎると、規制物質の含有を過小評価してしまう恐れがあります。
一方で細かく分けすぎると、管理データ量が膨大になり、運用負荷が高まります。
そのため、実際の分解可能性や設計上の構成を考慮し、現実的なレベルで整理することがポイントです。
社内で判断基準を明確にしておくことで、担当者によるバラつきを抑え、データの一貫性を保ちやすくなります。
重量・濃度計算
重量や濃度の算出は、RoHSやREACHなどの規制適合を判断するための重要な要素です。
各部品や均質材料ごとに、対象物質の重量を製品全体または均質材料に対してどの割合で含むかを確認します。
濃度の表し方には「%(重量比)」や「ppm」などがあり、いずれも基準となる母材の重量を明確にしておくことが大切です。
計算時は、四捨五入や単位換算の誤差にも注意が必要です。
サプライヤから提示されたデータをそのまま使用する場合も、基準や単位が異なっていないかを確認し、必要に応じて変換・補正を行います。
正確な重量・濃度データは、最終的な法規制判定の信頼性を左右するため、丁寧な確認が欠かせません。
ブラックボックス部品の扱い
市販の電子部品やモジュールなど、内部構造や材料情報が開示されない「ブラックボックス部品」は、多くの企業が直面する課題です。
こうした部品に対しては、次のような対応が一般的です。
- メーカーが提供するRoHS・REACH適合宣言書を入手する
- chemSHERPA形式などで部分的な情報提供を受ける
- 分析試験結果や第三者機関のデータを参考にする
すべての情報を完全に把握することは難しい場合もあるため、入手できた情報の範囲を明確にしておくことが大切です。
また、ブラックボックス部品を多く含む製品では、リスクレベルを整理し、優先的に追加確認や再依頼を行う体制を持つと効果的です。
変更管理(ECN/ECR)
部品の仕様変更や代替採用が発生した場合、環境BOMの情報も同時に見直す必要があります。
その際に活用されるのが、ECN(Engineering Change Notice)やECR(Engineering Change Request)といった変更管理プロセスです。
環境BOMを設計BOMと連携させておくことで、設計変更時に自動で対象部品を抽出したり、再確認が必要な箇所を特定しやすくなります。
更新後のデータには改訂番号を付与し、誰が・いつ・何を変更したかを明確に残しておくと、後からの追跡や監査時の説明がスムーズになります。
監査対応
監査では、提出した環境BOMの妥当性やデータの裏付けが確認されることがあります。
対応のためには、データの根拠資料(CoC、SDS、試験報告書など)を整理しておくことが重要です。
監査時に求められるのは「証拠として説明できる状態」であり、完全な分析データを常に求められるわけではありません。
ただし、データ更新履歴やサプライヤの回答記録など、トレーサビリティを示せる形で保管しておくと信頼性が高まります。
社内監査を定期的に行い、提出データの整合性を確認する仕組みを持つと安定した運用につながります。
グローバル運用
環境BOMは、海外拠点やグローバル取引を含む場合、複数地域の法規制に対応できる形で運用する必要があります。
各国で要求される物質リストや閾値、提出形式が異なるため、共通フォーマットを社内で定義しておくと管理がしやすくなります。
また、情報の言語や単位、タイムゾーンの違いにも注意が必要です。
海外サプライヤとのやり取りでは、英語や現地言語でのデータ交換が発生するため、翻訳ミスや数値表記の違いにも配慮します。
更新サイクルや責任分担を明確にし、全体を通じて一貫性のある情報を保つことが求められます。
AI/LLM活用
近年では、AIや大規模言語モデル(LLM)を活用した環境BOM運用の効率化も進みつつあります。
たとえば、次のような活用方法があります。
- SDSやCoCなどの文書から物質情報を自動抽出する
- 収集データの欠損や矛盾を自動で検出する
- 法規制リストの更新情報を自動で照合し、影響部品を提示する
AIはあくまで支援ツールであり、最終判断は人が行う必要がありますが、煩雑なデータ処理や初期確認を自動化することで、担当者の負担を軽減できます。
今後は、AIを活用した環境情報管理の効率化がさらに進むと見込まれています。
環境BOMを確実に運用していくためには、現場の実務知識とともに、こうした最新ツールの活用も視野に入れることが有効です。
スキーム別 実務ガイド
環境BOMを運用する上では、業界や取引先ごとに指定されるスキーム(データ形式)が異なる場合があります。
ここでは代表的な2つのスキームであるchemSHERPAとIMDSの実務上のポイントを紹介します。
いずれも法規制対応を効率的に進めるための枠組みとして活用されていますが、目的や使用環境が異なる点を意識しておくと運用がスムーズです。
chemSHERPAの実践
chemSHERPA(ケムシェルパ)は、日本国内を中心に広く利用されている化学物質情報の伝達スキームです。
RoHS指令やREACH規則などの国際的な規制に対応しながら、製品サプライチェーン内で共通形式のデータ共有を可能にします。
chemSHERPAには、用途に応じて次の2種類があります。
- chemSHERPA-AI(Article Information):完成品や部品レベルの情報を扱う
- chemSHERPA-CI(Chemical Information):材料や化学品レベルの情報を扱う
実務では、サプライヤからの情報収集や顧客への提出のどちらにも対応できるよう、両形式を理解しておくと役立ちます。
データを入力する際には、製品構成を階層的に整理し、化学物質や均質材料単位の情報を正確に登録することが求められます。
また、chemSHERPAツールの検証機能を活用すると、入力漏れや形式不備を防ぎやすくなります。
更新時には、法規制リストやバージョン情報を確認し、最新のフォーマットで再出力することが推奨されます。
chemSHERPAは定期的に更新されるため、古いバージョンのデータでは取引先が受理しない場合もあります。
IMDSの実践
IMDS(International Material Data System)は、自動車業界で標準的に利用されているグローバルな化学物質情報システムです。
自動車メーカー(OEM)とサプライヤが共通のデータベース上で部品構成と化学物質情報を共有できる仕組みとして運用されています。
IMDSでは、部品をツリー構造で登録し、材料や化学物質を階層的に紐づけていきます。
構成データには、部品番号、材料名、重量、CAS番号などの情報が含まれ、規制物質の有無を明確にすることが求められます。
登録内容は各OEMによって審査されるため、フォーマットの整合性や不備のないデータ作成が重要です。
また、GADSL(Global Automotive Declarable Substance List)との整合を確認することで、申告対象物質の漏れを防ぐことができます。
差し戻し(リジェクト)が発生する場合は、入力ルールや命名方法に不一致があるケースが多く、メーカーごとの要求仕様を確認して再提出を行います。
IMDSは国際的なデータ共有プラットフォームであるため、データの正確性だけでなく、改訂履歴や承認フローの管理も重視されます。
環境BOMと連携させることで、他業界との情報共有にも活用しやすくなります。
業界別の運用ポイント
環境BOMや化学物質情報管理の運用は、業界によって重点や運用ルールが異なります。
ここでは主要な産業分野ごとに、一般的な特徴と注意点を紹介します。
電子・電機
電子・電機分野では、RoHS指令やREACH規則への対応が中心になります。
部品点数が多く、サプライヤ層が複雑なため、chemSHERPAを用いたデータの一元管理が広く採用されています。
はんだやコーティング材など、微量成分の管理が必要なケースも多く、均質材料レベルでのデータ精度が重視されます。
法改正への対応頻度が高いため、定期的なリスト更新と再確認が欠かせません。
自動車
自動車業界では、IMDSを通じたデータ登録が標準プロセスとして定着しています。
各OEM(完成車メーカー)が独自のルールや入力要件を持つことが多く、それに合わせたデータ整形が必要です。
また、電動化や軽量化に伴い、新素材の採用が増えているため、材料変更時の迅速な更新体制が求められます。
GADSLやELV指令など、業界特有の物質リストも考慮して管理を行います。
産業機器
産業機器分野では、長期供給や部品共用化が前提となることが多く、環境BOMの更新性と履歴管理が重視されます。
構成が複雑な製品では、代替部品の選定や設計変更時に環境情報を参照できる体制が重要です。
電子部品、樹脂、金属など異なる素材が混在するため、データの階層構造を明確に保つことが有効です。
医療機器
医療機器業界では、製品安全や品質保証の観点から、環境法規制対応と合わせてリスクマネジメントが求められます。
RoHS適合が医療機器指令(MDR)に関連して求められる場合があり、対象範囲の正確な理解が重要です。
生体接触部品や滅菌材料など、通常のBOMでは扱わない特性を持つ部品もあるため、環境BOM作成時には慎重な確認が必要です。
消費財・玩具
消費財や玩具分野では、RoHSやREACHのほか、EN 71(玩具安全指令)や包装材関連の規制など、多様な基準への対応が求められます。
直接人体に触れる製品が多いため、特定物質の使用制限や表示義務が細かく定められています。
環境BOMは、製造委託先や海外サプライヤのデータ追跡に役立ちます。
特殊カテゴリ(電池/包装材 など)
電池や包装材などの特殊分野では、専用の規制や報告制度が設けられています。
電池では鉛、水銀、カドミウムなどの重金属管理が重点項目となり、包装材ではプラスチック再利用や含有物表示が求められる場合があります。
これらの分野では、一般的な環境BOMに加え、専用の報告書式や国別ルールを補完的に運用するケースが見られます。
ツールと体制づくり
環境BOMを安定的に運用するためには、データを扱う仕組みと、それを支える社内体制の両方が欠かせません。
個人の努力に依存する運用では長続きしにくいため、システム連携や役割設計を整えることで、業務効率と精度を両立しやすくなります。
PLM/ERP連携
環境BOMは、設計BOMや製造BOMなどと密接に関係しています。
そのため、PLM(製品ライフサイクル管理)やERP(基幹業務システム)との連携を検討することが有効です。
設計部門がPLM上で管理している部品構成情報を環境管理システムに連携すれば、二重入力を減らせます。
同様に、ERPの購買情報と連携することで、サプライヤごとの環境データを自動で紐づける仕組みも構築できます。
これらの連携は一度にすべてを実施する必要はありません。
まずはデータの整合性を優先し、手動更新から自動連携へと段階的に移行する形が現実的です。
マスタ設計(物質リストDB)
環境BOM運用の基礎となるのがマスタデータの整備です。
ここでいうマスタとは、化学物質リストや部品・材料の共通情報を指します。
具体的には、以下のような情報を統一的に管理します。
- 規制対象物質リスト(RoHS、REACH、GADSLなど)
- 含有制限値や閾値の基準
- 部品・材料ごとの標準属性(材質、重量、サプライヤ名など)
マスタ設計を行う際は、将来的な法改正や新物質追加を想定し、更新しやすい構成を考慮します。
法規制の変更を即座に反映できるよう、外部データとの連携や自動更新機能を取り入れることも有効です。
役割分担
環境BOMの作成・更新・管理には複数の部門が関わります。
そのため、誰がどの範囲を担当するかを明確にしておくことが重要です。
一般的には次のような分担が想定されます。
- 設計部門:新規部品や代替品の選定時に環境情報を確認
- 調達部門:サプライヤからの環境データ収集と品質確認
- 品質・環境部門:法規制の更新管理、社内教育、監査対応
- 情報システム部門:ツール導入・システム連携の技術支援
役割を明確にすることで、データの重複や抜け漏れを防ぎ、全体の効率を高めることにつながります。
KPIと可視化
環境BOMの運用状況を把握するためには、KPI(重要業績評価指標)を設定し、可視化することが有効です。
KPIは数値で管理できるシンプルな指標が望ましく、代表的なものとして以下が挙げられます。
- サプライヤ情報の回収率
- データ更新までの平均リードタイム
- 不備や差戻し件数
- 年次法規改訂への反映完了率
これらの指標を定期的に確認し、改善ポイントを共有することで、部門間の連携を強化できます。
ダッシュボード化してリアルタイムで進捗を見える化する仕組みを導入する企業も増えています。
外部リソース活用
自社だけで環境BOMのすべてを運用するのは難しい場合もあります。
そのようなときは、外部リソースの活用を検討することが現実的です。
主な例としては以下のようなものがあります。
- 化学分析や試験データ取得を専門機関に委託する
- 法規制や物質リスト更新を外部データベースから自動取得する
- 環境情報管理に詳しいコンサルタントやシステムベンダーに支援を依頼する
社内での知見を育てつつ、必要に応じて外部の知識やツールを取り入れることで、限られたリソースでも効率的な運用が可能になります。
環境BOMは、システムと人の両輪で運用される仕組みです。
ツールをうまく活用しながら、社内の責任分担と情報の流れを明確に整えることが、長期的な安定運用の鍵になります。
チェックリスト&テンプレート
環境BOMを実務で活用する際には、データの精度と提出品質を確保するための仕組みづくりが重要です。
ここでは、現場で使いやすい代表的なチェック項目やテンプレートの考え方をまとめます。
実際の書式や内容は、企業や取引先の要件に応じて調整することを前提としています。
サプライヤ依頼テンプレ
サプライヤに環境データを依頼する際は、依頼内容が明確であるほど回答精度が高まります。
そのため、和文と英文の両方に対応したテンプレートを用意しておくと便利です。
依頼書には、次のような要素を盛り込むのが一般的です。
- 対象製品または部品番号の明示
- 対応すべき法規制(RoHS、REACHなど)
- 回答形式(chemSHERPA形式や独自フォーマットなど)
- 回答期限と問い合わせ窓口
- 秘密保持や再利用の取り扱いに関する一文
依頼書を定型化しておくことで、社内の依頼内容のばらつきを抑え、取引先とのやり取りをスムーズに進めやすくなります。
均質材料分解チェック
環境BOMでは、部品や製品を「均質材料」単位で整理する必要があります。
このため、均質材料の切り分けが適切に行われているかを確認するチェックリストが役立ちます。
主な確認ポイントは以下の通りです。
- メッキ、塗装、接着などの表面処理層が分離されているか
- 樹脂と金属、または異種材が正しく区分されているか
- 混合材の組成比が明確になっているか
- サプライヤから提供された構成情報が実際の製品仕様と一致しているか
このチェックを設計段階で行うことで、後工程でのデータ修正や不一致のリスクを減らすことができます。
判定計算シート項目
環境BOMの中核となるのが、法規制への適合判定です。
RoHSやREACHの閾値判定を自動または手動で行うための計算シートを準備しておくと便利です。
シートには、以下のような項目を設けておくと運用しやすくなります。
- 均質材料単位の質量
- 含有化学物質名とCAS番号
- 含有濃度(%またはppm)
- 規制物質リストとの照合結果(該当/非該当)
- 判定結果(適合/不適合/確認中)
- 判定根拠や備考欄
このように構造化しておくと、変更時の再判定が容易になり、過去の記録とも比較しやすくなります。
提出前の最終チェック
環境BOMを顧客や当局に提出する前には、内容を最終確認する工程を設けることが望ましいです。
提出直前に確認する主な項目として、次のような点があります。
- 対象範囲やバージョンの整合性
- サプライヤ未回答や空欄データの有無
- 単位や濃度表記の統一
- 証拠書類の添付状況
- chemSHERPA/IMDSファイルの検証結果(エラー有無)
- 最新の法規リストとの照合
この確認を定常業務として仕組みに組み込むことで、提出後の差戻しや修正依頼を最小限に抑えられます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 環境BOMと通常BOMの違いは何ですか?
A. 通常のBOM(部品表)は、製品を構成する部品や材料、数量などを管理する設計情報です。
環境BOMは、その情報に加えて化学物質や環境負荷物質のデータを付与し、環境法規制への適合を確認できるようにしたものです。
つまり、設計のためのBOMと、環境管理のためのBOMという目的の違いがあります。
Q2. 「均質材料」とは何を指しますか?
A. 均質材料とは、化学的または機械的に分離できない最小単位を指します。
たとえば、メッキ加工された金属部品では、金属部分とメッキ層をそれぞれ別の均質材料として扱います。
この定義を誤ると含有物質の評価がずれるため、実際の分解可能性を考慮して判断することが重要です。
Q3. RoHSの閾値はどのように計算しますか?
A. RoHS指令では、鉛やカドミウムなどの特定有害物質が、均質材料中で規定された閾値を超えていないかを確認します。
通常は、対象物質の質量を均質材料全体の質量で割り、重量比(%またはppm)として算出します。
閾値を超える場合は、除外用途の該当有無を確認したうえで判断します。
Q4. REACHとSCIPにはどのような関係がありますか?
A. REACH規則では、SVHC(高懸念物質)が0.1wt%を超える場合、情報開示が求められます。
EU市場で販売する場合、SCIPデータベースへの届出が必要となるケースがあります。
届出要否は製品の用途や流通範囲によって異なり、最新の規制動向を確認することが望まれます。
Q5. chemSHERPAのAIとCIはどう違うのですか?
A. chemSHERPAには2種類のデータ形式があります。
AI(Article Information)は製品・部品レベルの情報を、CI(Chemical Information)は材料や化学品レベルの情報を扱います。
AIとCIを連携させることで、上流から下流まで一貫したデータ管理が可能になります。
Q6. IMDSで差戻しが起こるのはなぜですか?
A. 差戻し(リジェクト)は、データ形式や階層構造の不備、命名ルールの不一致などが原因になることがあります。
自動車メーカー(OEM)ごとに入力要件が異なるため、事前に要求仕様を確認し、登録内容をそれに合わせることが重要です。
Q7. 試験データは必ず必要ですか?
A. すべての部品で分析試験データが求められるわけではありません。
多くの場合、サプライヤ声明書やSDS(安全データシート)などで代替可能です。
ただし、重要部品や高リスク品では、分析データを補足資料として添付することがあります。
Q8. 秘密配合がある場合、どのように対応すべきですか?
A. 化学製品などでは、企業機密のため一部成分が非開示となる場合があります。
その場合は「コンフィデンシャル」として申告し、非開示範囲やリスク管理方法を説明します。
必要に応じて秘密保持契約(NDA)を結び、情報共有を行うケースもあります。
Q9. 環境BOMはどのくらいの頻度で更新すればよいですか?
A. 法規制や製品構成の変更が発生したときに随時更新するのが基本です。
また、少なくとも年1回程度、定期的に全体を見直しておくと、古いデータのまま運用するリスクを減らせます。
Q10. グローバル対応ではどの国の法規制を優先すべきですか?
A. 製品が販売される主要市場(EU、北米、中国など)の法規制を優先して対応することが一般的です。
RoHS、REACH、China RoHS、Proposition 65などの主要規制をカバーしておくと、多くの地域で共通の基盤として活用できます。
Q11. PFAS(有機フッ素化合物)への対応は必要ですか?
A. PFASは今後、各国で段階的に規制が強化される可能性があります。
現時点では、対象物質を把握し、含有有無を早期に確認する体制を整えておくことが推奨されます。
新規制の動向に注意し、必要に応じて代替材料を検討することが望まれます。
Q12. AIやLLMを使うときに注意することはありますか?
A. AIや大規模言語モデル(LLM)は、SDSやCoCなどの文書から化学物質情報を抽出する補助ツールとして活用できます。
ただし、生成された結果をそのまま採用せず、必ず人の確認を経ることが前提です。
AIは作業効率を高める手段であり、最終的な判断は専門知識を持つ担当者が行うことが適切です。
まとめ
環境BOMは、製品に含まれる化学物質や環境負荷物質の情報を整理し、法規制や顧客要求に対応するための重要な仕組みです。
RoHS指令やREACH規則など、世界的に拡大している環境法規制に対して、正確で更新可能なデータ管理体制を整えることが、企業の信頼性や取引継続に直結します。
本記事では、環境BOMの基本的な考え方から、実際の構築手順、chemSHERPAやIMDSなどのスキーム運用までを体系的に整理しました。
さらに、実務で発生しやすい課題(均質材料の判断、データ精度、サプライヤ対応など)に対する実践的なノウハウも紹介しています。
環境BOMの運用を成功させるためには、以下の三点が特に重要です。
- 正確で再利用しやすいデータ基盤の整備
- 設計・調達・品質・環境の連携による体制づくり
- ツールと最新スキームの活用による効率化
環境対応は単なる法令遵守ではなく、企業の社会的責任(CSR)やサプライチェーンの信頼性にも直結する要素です。
小さな一歩でも、正確な情報整理と仕組みづくりから始めることが、長期的なリスク回避と持続的な事業運営につながります。
これから環境BOMの整備に取り組む方は、まずは自社の現状を把握し、優先度の高い製品や部品から整理を進めることが効果的です。
一度構築した仕組みを継続的に更新・改善していくことで、将来の規制強化にも柔軟に対応できる体制を築けるでしょう。