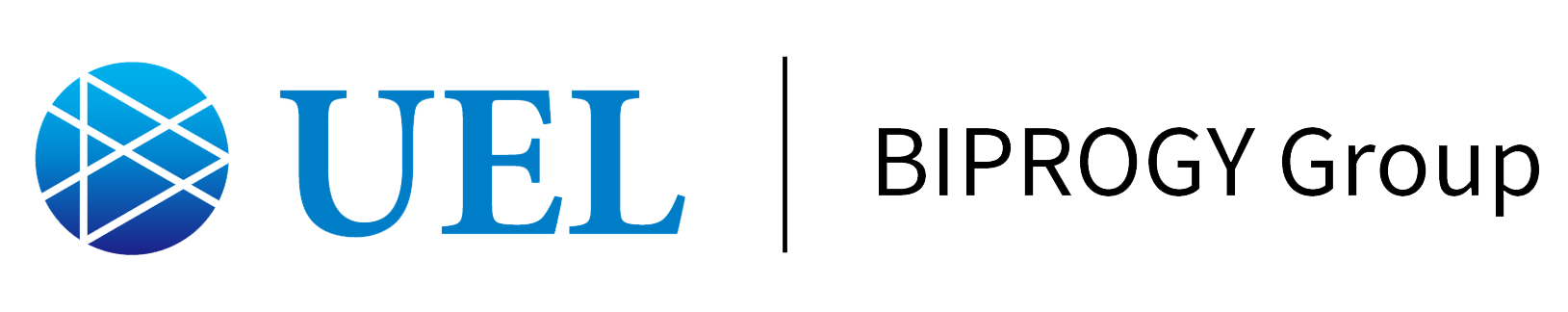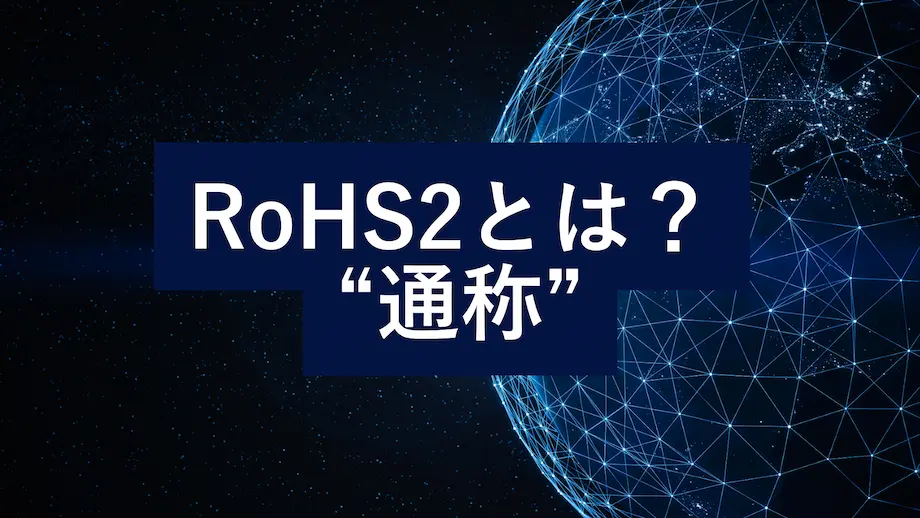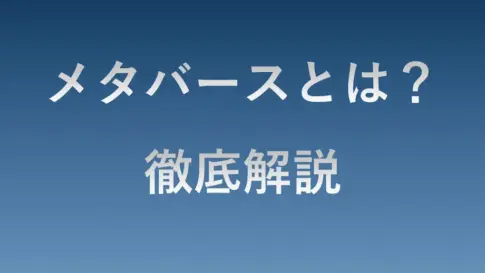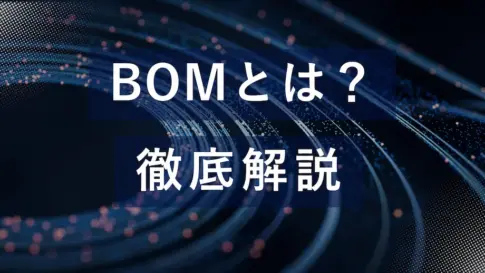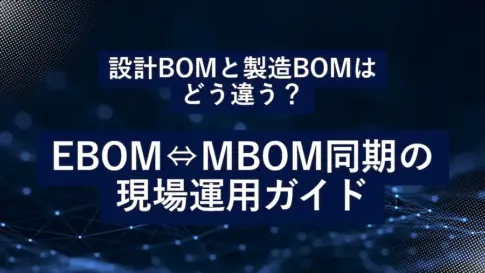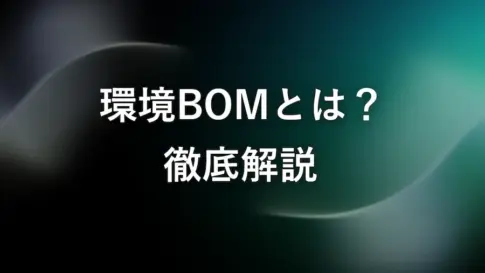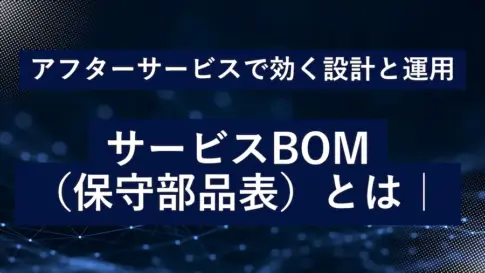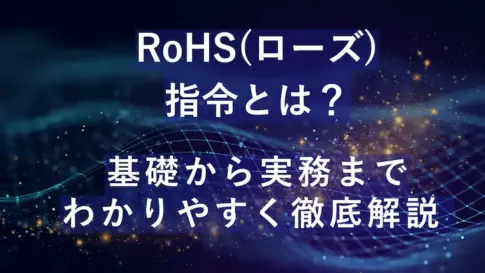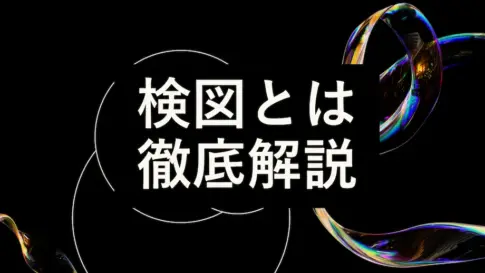RoHS2という言葉は広く使われていますが、実はこれは正式な法令名称ではなく、あくまで“通称”です。そのため、指している内容や範囲が人や組織によって異なり、現場での混乱や誤解を招く原因となることがあります。
本記事では、RoHS2という用語の正しい理解と、当社における明確な定義をご紹介いたします。

監修・執筆:UEL株式会社編集部
UEL株式会社のTechデザイン企画部と現場に精通した社内有識者が監修・執筆しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の企業・環境・状況への適用や効果を保証するものではありません。内容の利用は読者ご自身の判断と責任にてお願いいたします。参考としてご活用ください。
目次
RoHS2とは?“通称”
まず最初に押さえておきたいのは、「RoHS2」は“通称”で法律上の正式な名称ではないという点です。
- 正式名称:Directive 2011/65/EU(改正RoHS指令)
- 「RoHS2」という名称は業界内での便宜的な呼称であり、EU公式文書内では使用されていません
- そのため、「RoHS2」という言葉が何を意味するのかは、使う側の定義によって異なることがあります
このような背景から、社内外で一貫した定義を用いることが重要になります。
当社における「RoHS2」の定義
当社では、RoHS指令の改正フェーズごとに以下のように明確に区分しております。
| 区分 | 内容 | 施行年 | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| RoHS2 | 適用範囲の拡大、およびCEマーキングの義務化 | 2013年施行 | いわゆる「2本柱」と呼ばれる主要な改正点 |
| RoHS2.x | 10種類の特定有害物質(フタル酸エステル類)の追加 | 2019年施行 | 一部では「RoHS3」とも呼ばれるが、当社では使用しません |
このように、2013年施行の改正内容(適用範囲の拡大とCEマーキング義務化)をRoHS2と定義し、
その後の2019年に適用された10物質制限の追加は、RoHS2.xとして区別しています。
なぜ「RoHS2」と「RoHS2.x」を区別する必要があるのか
RoHS関連の実務では、次のようなケースで混乱が生じやすくなります。
- 「RoHS2」と聞いて10物質制限が含まれていると誤解してしまう
- 「RoHS3」という表現が社内・業界内でバラバラに使われている
- 改正の施行時期や対象範囲が不明確なまま運用されている
こうした状況では、技術文書の作成範囲や適合証明の要否、CEマークの有効性確認などに影響が出る可能性があります。
RoHS2とRoHS2.xを明確に区別し、自社製品の製造・出荷時期とも照らし合わせたうえで正しく運用を行うことが不可欠です。
簡単にわかるRoHS2(2013年施行)
RoHS2(通称)とは、2011年に公布されたEU指令「Directive 2011/65/EU」が2013年に施行された段階の内容を指します。この時点で導入された主な改正ポイントは以下の「2本柱」で構成されています。
RoHS2の2本柱
| 柱 | 内容 | 概要 |
|---|---|---|
| ① | 適用範囲の全面拡大 | 従来対象外だった医療機器や産業用大型設備まで規制対象を拡大し、EEEカテゴリ1〜11を網羅 |
| ② | CEマーキングの義務化 | 自己宣言ではなくCEマーキング+適合宣言書(DoC)+技術文書の保管を義務付け、法的整合性を強化 |
EEE:Electrical and Electronic Equipment(電気・電子機器)の略称
- 産業用大型設備(工作機械など)は適用対象外となります。追加されたのは、カテゴリ8(医療用機器類)、カテゴリ9(監視・制御機器類)となりますので以下のように変更してください。従来対象外だった医療機器や監視・制御機器が規制対象となり、EEEカテゴリ1~11までに対象製品が拡大。
- CEマーキング義務化RoHS指令の他、当該製品に適用される各指令や規則を確認し、適合宣言書(DoC: Declaration of Conformity)を作成。禁止対象物質の非含有や適用除外での利用を技術文書に示し、製品へのCEマークを表示する。※製品サイズや性質上、製品に直接表示が不可能な場合、パッケージや取扱説明書へ表示といった代替方法が認められる。
押さえておくべきポイント
- 適用範囲の拡大により、RoHS非対応製品の業界(医療機器、計測機器等)からの化学物質調査が増え、代替物質の検討が必要に。
- CEマーキング義務化にRoHS指令が加わることにより、製造者は表示内容の見直し、輸入者・販売者は保管・輸送時の適合性の担保。
- 技術文書やDoCはEN IEC 63000のガイドライン準拠し、最低10年間の保管が必要です
- この改正により、製品設計段階からの化学物質管理・文書整備が実務要件となった点が大きな変化です
なぜこの2本柱が重要なのか?
RoHS2の目的は、有害物質の排除だけでなく、EU域内での製品流通の透明性と安全性を高めることにあります。
この2本柱によって、企業は単に規制値を満たすだけでなく、製品の設計・調達・管理全体において責任を果たす体制が求められるようになりました。
RoHS2.x (2019施行) 10物質追加のポイント
RoHS2.xとは、RoHS指令(Directive 2011/65/EU)の2015年改正によって、新たに4種類のフタル酸エステル類が制限対象として追加され、2019年7月から適用されたフェーズを指します。
この段階を一部では「RoHS3」と呼ぶこともありますが、本記事では「RoHS2.x」として区別しています。
RoHS2.xで追加された4物質
| 物質名 | 主な用途 | 規制理由(有害性) |
|---|---|---|
| DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル) | PVCケーブル、コーティング材 | 生殖毒性・内分泌かく乱作用 |
| BBP(フタル酸ブチルベンジル) | 接着剤、合成皮革 | 生殖毒性、胎児への影響 |
| DBP(フタル酸ジブチル) | 印刷インキ、塗料 | 発達毒性、内分泌かく乱作用 |
| DIBP(フタル酸ジイソブチル) | 合成レザー、塗料、接着剤等 | DEHPと類似の毒性 |
制限内容のポイント
- 追加された4物質により、RoHS規制物質は合計10種類に拡大されました
- 規制対象となる濃度は、均質材料単位で0.1%以下(カドミウムは0.01%)
- 製品全体の平均ではなく、最小単位の部品レベル(ねじやケーブルの被覆等)とその材質レベル(高合金鋼、○○樹脂等)での管理が求められます。
- 適合を証明するには、スクリーニング+化学分析による裏付けが必要です
実務で押さえておきたい検査ステップ
- XRFスクリーニングによる6物質の初期確認
- フタル酸4物質は別途スクリーニング試験(赤外分光、迅速判定キットなど)
- 陽性反応が出た部品はGC-MS等で定量分析し、閾値クリアを確認
- RoHS適合品に対しての製造ライン、梱包材、輸送/保管時のフタル酸エステルの汚染リスク対策の実施
なぜRoHS2.xが重要なのか?
RoHS2.xによる10物質制限の追加は、単なる「物質の数が増えた」以上の意味を持ちます。
これにより、企業には次のような対応が求められるようになりました。
- 材料情報のより精緻なトレーサビリティ
- サプライヤー調査の項目見直しと定期更新
- フタル酸を含まない設計への事前配慮(DFE:Design for Environment)
まとめ
- RoHS2.xでは4つのフタル酸エステル類が新たに制限対象となり、合計10物質に
- 濃度は「均質材料」単位で評価され、スクリーニング→詳細分析の流れが不可欠
- RoHS2(2013年施行)とは区別し、適切に文書・試験・設計対応を進めることがRoHS適合の鍵となります
このフェーズを正しく理解することで、将来の追加規制(RoHS10+α)にも柔軟に対応できる体制づくりが可能になります。
【実務】RoHS2/RoHS2.x 適合の最短ロードマップ
RoHS2およびRoHS2.xに適合するためには、サプライヤーからの材料情報取得からCEマーキング表示まで、段階的かつ確実なプロセスが求められます。
以下に、実務担当者が押さえるべき最短かつ確実な手順をご紹介します。
ステップ①:サプライヤーから部材情報を取得する
まず最初に行うべきは、製品を構成するすべての部材について、材料情報を正確に把握することです。
- 使用ツール例:chemSHERPA、JAMP AIS、IPC-1752A など
- 情報の内容:含有化学物質、CAS番号、濃度、用途、部材ごとの分類など
- 目的:10物質の含有有無を把握し、スクリーニング・分析対象を効率化するため
※特にchemSHERPAは、RoHS・REACH・その他規制にも対応しており、共通基盤として活用可能です。
ステップ②:三段階の分析フローで適合性を評価
取得した情報をもとに、以下の三段階分析を実施することで、RoHS適合を科学的に証明します。
| 分析段階 | 対象物質 | 方法 | 概要・目的 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | RoHS旧6物質 | XRFスクリーニング | 非破壊で迅速に全数検査可能。リスク判定の初期工程 |
| 第2段階 | フタル酸エステル類4種 | 専用スクリーニング検査 | 簡易検査(IR、熱抽出、判定キットなど)で選別 |
| 第3段階 | 全10物質 | GC-MSやICP-OESによる詳細分析 | 数値データにより閾値(0.1%/0.01%)未満を証明 |
※スクリーニングで「グレー」または「陽性」とされた部品は必ず第3段階へ。
ステップ③:技術文書をEN IEC 63000に準拠して電子保管
試験結果や材料情報をもとに、RoHS技術文書一式を整備します。
以下のガイドラインに準拠することが推奨されます。
- 規格:EN IEC 63000(旧IEC 63000)
- 文書内容の例:部品構成図、BOMリスト、試験報告書、サプライヤー資料、リスク評価、工程管理書類など
- 保管形式:電子化されたフォルダで10年間保存可能な状態にするのが望ましい
ステップ④:DoC(適合宣言書)署名 → CEマーキング表示 → 10年間の保管
すべての情報が整ったら、最終的な適合宣言書(DoC)を作成・署名し、CEマーキングを製品に表示します。
- DoCには次のような内容を明記
- 製品名、型番
- 適用指令(RoHS2)
- 該当規格(EN IEC 63000 等)
- 製造者情報・署名者氏名
- 発行日と識別番号(任意)
- CEマーキング表示要件
- 最小高さ5mm、視認性・判読性のある位置に貼付
- 包装や取扱説明書にもトレーサビリティ情報を明記
- DoCと技術文書一式は製造終了から10年間保管し、要求があれば即時提出できる体制を整備します。
まとめ:RoHS2/2.x対応の実務は“段階と根拠”がカギ
RoHS適合は単なる試験結果の提示ではなく、データに基づいたリスク評価・証明責任の履行が求められる制度です。
下記の4ステップを押さえることで、EU市場での安定供給と規制対応の信頼性を同時に実現できます。
RoHS2/RoHS2.x 適合の基本ステップ
- chemSHERPA等による部材情報の取得
- XRF・フタル酸スクリーニング・GC-MSの三段階分析
- EN IEC 63000準拠の技術文書を整備・電子保管
- DoC署名・CE表示・10年保管の体制構築
この流れを理解し、組織的に運用できることが、RoHS対応の“実務力”といえるでしょう。
非適合のペナルティと社内是正フロー
RoHS2/RoHS2.xに適合しない製品をEU市場で流通させた場合、重大な法的・経済的リスクが発生します。
適合性の不備が発覚すると、製造者・輸入者・販売者のいずれも厳しい対応を求められ、事後の是正には多大な労力がかかるため、事前にフローを理解し備えておくことが重要です。
RoHS非適合が発覚した際の主なリスク
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| 市場での販売停止 | 対象製品の流通が即座に禁止され、出荷済み分は回収対象に |
| リコール命令 | 顧客・小売業者を通じて製品の回収を求められる |
| 行政罰・罰金 | 加盟国ごとに異なるが、数万〜数十万ユーロ規模の制裁が科されることもあり得る |
| 刑事責任(重大時) | 故意または重大過失があったと判断された場合は、刑事訴追の可能性も |
| ブランド信頼低下 | 顧客・取引先・市場全体からの信頼を大きく損なうリスク |
特にCEマーキングに関わる規制であるため、検査当局による抜き打ち検査での摘発事例も少なくありません。
【社内対応】非適合が発覚した場合の是正フロー
万が一、RoHS非適合が確認された場合には、以下のような社内是正プロセスを速やかに実行することが求められます。
ステップ1:関係部署への即時連絡と事実確認
- 品質保証、技術、生産、法務、営業部門などに速やかに報告
- 対象製品の型番、出荷時期、影響範囲を特定
- 適合証明書や試験データを再確認し、文書上の齟齬や抜け漏れがないかを精査
ステップ2:原因調査と分析
- 使用部材・サプライヤー変更の有無
- スクリーニング試験の工程ミスや分析データの誤記載などを洗い出す
- 必要に応じて再試験や再調査を実施
ステップ3:是正措置の実施
- 該当ロットの回収または廃棄
- 再発防止策としての文書管理ルール改訂や検査体制の強化
- CEマーキング再付与の判断(場合によっては再取得)
ステップ4:当局報告と証拠提出
- 要請に応じて、技術文書・DoC・分析データ・是正報告書を提出
- 指定期間内に是正完了の証明を提出する義務あり(国によって異なります)
是正処置報告の主な内容
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 不適合の詳細 | 対象物質、測定値、超過理由、関連部品の特定 |
| 原因分析 | 仕入先の材料誤申告、検査漏れ、設計仕様の不備など |
| 是正措置の内容 | 部品変更、再設計、検査体制強化、教育の実施など |
| 再発防止策 | サプライヤー契約の見直し、内部監査強化、マニュアル改訂等 |
| 添付資料 | 試験報告書、写真、修正後のBOM、教育記録など |
まとめ:リスク回避には“事前管理”と“是正体制”の整備が不可欠
- RoHSの非適合は即座にビジネスへ深刻な影響を与えるリスクがあります
- 罰則や回収よりも怖いのは、企業全体の信用喪失と調達ストップ
- 日常的な材料証明のチェックや検査体制の標準化とともに、万が一に備えた社内の是正フロー構築が重要です
「いつか起きるかもしれない」ではなく、「いつ起きても即対応できる」状態にしておくことが、RoHS時代の品質保証における新常識です。
RoHSの今後を見据える―RoHS10+αとPFAS規制の動向と備え
RoHSの次なる改正は、既存10物質の枠を超えた「RoHS10+α」の拡張が予定されており、特にPFAS(有機フッ素化合物)規制との連動が大きな焦点になっています。
企業としては、将来の規制対象を見据えた事前対策が重要です。
現時点で追加が検討されている物質例
| 分類 | 物質名 | 主な用途 | 懸念される有害性 |
|---|---|---|---|
| 難燃剤系 | TBBPA(テトラブロモビスフェノールA) | プリント基板 | 内分泌かく乱・長期残留性 |
| 難燃剤系 | MCCP(中鎖塩素化パラフィン) | ケーブル被覆・PVC添加剤 | 発がん性・生殖毒性 |
| 難燃剤系 | ATO(三酸化アンチモン) | 難燃剤との相乗効果 | 発がん性分類(Cat.2) |
| 金属化合物 | コバルト塩類 | リチウムイオン電池、顔料など | 呼吸器感作、発がん性 |
| 金属化合物 | インジウムリン化物 | マイクロLED、光通信素子 | 肺毒性、リサイクル困難 |
| 金属化合物 | ベリリウムおよび化合物 | 放熱板、接点材料 | 吸入リスク、発がん性 |
PFASとの連携規制にも要注意
- PFAS(有機フッ素化合物)については、EUで1万種以上を対象とした包括規制案が進行中
- フッ素系潤滑剤や防汚コーティングなど、電子機器部品に広く使われる素材が該当する可能性があります
- RoHSとPFASの規制対象が重なるリスクがあるため、今後の法制度動向を注視しつつ、素材変更や代替計画の立案が求められます
今のうちから取り組むべきこと
- 高リスク物質の含有有無を把握し、代替品の調査を進めておく
- 化学物質データベース(例:IEC62474)を使った設計初期段階のリスク評価
- 取引先と連携し、将来規制に対応できる材料選定・文書整備の体制を整備
将来のRoHS拡張に備え、“今は規制対象外”の物質にも目を向けた対応が、環境対応の先手となります。
FAQ
Q1. 「RoHS2」と「RoHS2.x(RoHS3)」はどう違うのですか?
RoHS2は2013年施行の2本柱(適用範囲拡大・CEマーキング義務化)を指し、RoHS2.xは2019年施行の10物質制限追加を指します。当社ではこのように明確に使い分けています。
Q2. CEマーキングの取得に必要な最小要件は?
技術文書(EN IEC 63000準拠)と適合宣言書(DoC)を整備し、製品または包装にCEロゴを貼付することが必須です。文書は製造終了後10年間の保管義務があります。
Q3. PFASとRoHSは別の規制ですか?連携する可能性は?
A.はい、RoHSとは別の規制で、対象物質は基本的には重複しません。対象物質は約10,000種類にも及びます。REACH規則で包括的に制限案が出されています。但し、PFASは、PCB(プリント基板)、ケーブル・ワイヤー、機能性フィルム等の電子機器部材によく使用されている物質のため、RoHSと同様に電子電機機器の製品設計時の材料選定に大きな影響があります。
Q4. 10物質制限に対応するスクリーニング方法は?
RoHS旧6物質はXRFによる迅速検査が可能ですが、フタル酸エステル類は専用の簡易スクリーニング→GC-MSなどでの確定分析が必要です。
Q5. 適合証明ができなかった場合のリスクは?
税関での差止め、リコール、罰金の可能性があります。取引停止や顧客信用の失墜にもつながるため、文書とデータの整備が極めて重要です。
まとめ
- 「RoHS2」は正式名称ではなく、Directive 2011/65/EU の通称です
- 当社では、「2013年施行の2本柱(適用範囲拡大・CEマーキング)」をRoHS2、
「2019年施行の10物質追加」をRoHS2.xとして明確に区分しています - 社内外の混乱を防ぐためにも、用語の定義と実務上の運用ルールの統一が不可欠です