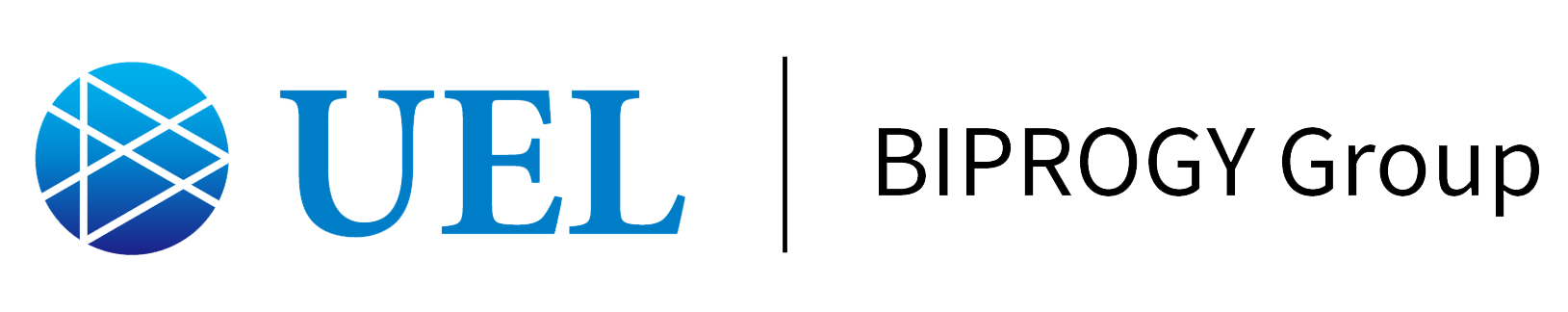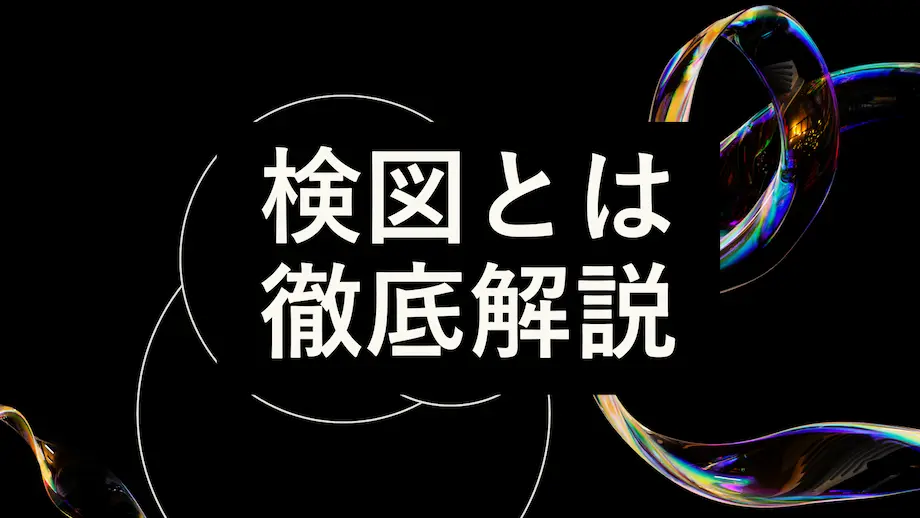検図は、図面のミスを未然に防ぎ、製造品質を直接左右する極めて重要な工程です。
図面の精度や正確性は、その後の製造工程や最終製品の品質、コスト、納期に大きく影響します。検図工程を徹底することにより、図面上のミスや不備によるトラブルを防ぎ、製造品質の向上およびコスト削減を実現できます。

監修・執筆:UEL株式会社編集部
UEL株式会社のTechデザイン企画部と現場に精通した社内有識者が監修しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の企業・環境・状況への適用や効果を保証するものではありません。内容の利用は読者ご自身の判断と責任にてお願いいたします。参考としてご活用ください。
目次
検図が重要である理由
検図が重要な理由は大きく3つあります。それは「品質向上」「トラブル防止」「コスト削減」です。
- 品質向上
検図を適切に行うことで、図面の正確性が高まり、結果として製品の精度や品質も向上します。誤った図面で製造を進めると、再作業や不良品の発生などのリスクが高まり、製造品質が低下するためです。 - トラブル防止
検図工程で図面の間違いや見落としを早期に発見・修正することで、製造工程に入る前にトラブルの発生を未然に防ぐことが可能になります。これにより、納期遅延や工程間の混乱などを防止できます。 - コスト削減
図面の不備によるトラブルが発生すると、その修正には多大な労力と費用が発生します。検図工程に力を入れれば、事前に問題を発見できるため、余計なコストや工数の発生を抑えられます。
検図の具体的な方法と流れ
検図を効果的に行うためには、「明確な手順」を設定し、それに沿って進めることが重要です。
具体的には、以下のような流れと方法で進めます。
① 検図準備
まず、検図を始める前に必要な準備を整えます。
- 設計図面・仕様書の準備
検図対象となる図面と、それに関連する仕様書や設計基準書をそろえます。 - 確認基準の設定
検図を行うための具体的なチェック項目(寸法・公差・材料・加工方法など)をあらかじめ決めておきます。
② 一次検図(全体確認)
次に、図面全体を大きな視点で素早くチェックします。
- 図面全体の整合性確認
大きな誤りや抜け漏れがないか、寸法記載や注記の明らかなミスがないかを全体的に確認します。 - 関連図面との整合性チェック
複数の図面がある場合、相互間での矛盾がないかを確認します。
③ 二次検図(詳細確認)
全体確認が終わった後は、より細かな確認を行います。
- 寸法・公差の詳細チェック
各寸法が設計仕様や基準書に正しく従っているか、公差が適切に設定されているかを確認します。 - 加工方法・材料の妥当性確認
指定された加工方法や材料が設計意図や実際の製造工程に適しているかをチェックします。 - 加工性や組み立て可能性の確認
加工や組み立てに問題が発生しないか、作業現場を想定しながらチェックを行います。
④ 修正指摘・再確認
確認した結果を設計担当者に伝え、問題箇所を修正してもらいます。
- 指摘事項の明確化
具体的な修正内容を明確に伝え、設計者との間で認識を一致させます。 - 修正内容の再確認
修正が完了した図面を再度チェックし、指摘事項が適切に反映されていることを確認します。
⑤ 検図の完了・承認
最終的に問題がないことを確認し、検図完了として図面を承認します。
- 検図記録の作成
検図で確認した内容や修正履歴を記録・保存し、後々のトラブルや確認に備えます。 - 図面の正式承認
最終的な確認が終わった図面を承認し、製造現場へ提供します。
このように検図工程を体系的に進めることで、図面の精度と製品の品質を確実に高められます。
検図の具体的なポイント
検図作業で特に確認すべき項目
検図作業において特に重要なのは、寸法・公差、材料仕様、加工指示、図面間の整合性など、製品品質に直接関わる項目です。具体的には以下の項目を優先的にチェックしましょう。
- 寸法・公差の正確性
- 製品の寸法や許容差が設計基準や仕様書に沿っているかを徹底確認します。寸法誤差は、製品の不良につながる直接的要因となります。
- 材料仕様の妥当性
- 指定された材料が用途や加工条件に適しているかを確認します。材料の誤りや曖昧な指定は製造上のトラブルの原因となります。
- 加工方法や表面処理の明確性
- 図面に記載された加工方法、表面処理方法、仕上げ指示が明確で現場で混乱なく実施可能かを確認します。
- 図面間の整合性
- 複数の図面を使用する場合は、部品図・組立図間での仕様の食い違いや矛盾がないかを確認します。
見落としがちなポイントと注意点
検図で見落としがちなポイントは「寸法の抜け漏れ」「図面内の矛盾」「加工性の考慮不足」です。以下のような注意点を意識して作業を行いましょう。
- 寸法の抜け漏れに注意
- 寸法が一部記載されていない箇所や、基準寸法・基準位置の曖昧さがないかを意識的にチェックします。
- 図面内の矛盾を確認
- 一つの図面内で仕様が矛盾することがあります。寸法、公差、注記などが整合性を持っているかを再確認します。
- 加工性を考慮する
- 設計上は問題ない図面でも、現場で加工が難しい場合があります。加工現場をイメージし、加工が容易で合理的かどうかを確認することも大切です。
こうした具体的な確認ポイントを徹底することで、製造品質の向上に直結する精度の高い検図が可能になります。
従来の検図方法の課題と解決方法
紙ベースや2D検図の問題点
従来の紙ベースや2D検図は「ミスの見落としリスク」「作業効率の低下」「理解のしにくさ」という課題を抱えています。具体的な問題点は以下の通りです。
- ミスの見落としリスク
- 2D図面は視覚的に平面的なため、立体的な形状や複雑な構造において誤りを見落とす可能性が高くなります。
- 作業効率の低下
- 紙ベースや2D図面では、修正・再確認の度に大量の図面を再出力する必要があり、時間とコストがかかります。
- 理解のしにくさ
- 2D図面のみでは完成品の全体像を把握しづらく、特に複雑な形状や組立構造では設計意図の伝達が難しくなります。
3D検図技術による改善策
これらの課題を解決するのが3D検図技術です。3D検図を導入することで、検図精度の向上や作業効率化が実現します。その具体的な改善策は以下の通りです。
- 立体的な視覚化でミスを低減
- 3Dモデルを用いることで複雑な形状を直感的に把握できるため、寸法や形状のミス、干渉などのトラブルを迅速に発見し、未然に防止できます。
- 作業効率の向上
- 3Dデータを直接修正・確認できるため、図面の再出力や手作業による修正工程が不要となり、検図工程が大幅に効率化されます。
- 設計意図の明確化
- 3Dモデルは設計者の意図を分かりやすく伝達できるため、関係者間の誤解や伝達ミスが減少し、円滑なコミュニケーションを実現します。
このように、3D検図技術を活用することで従来の検図方法が持つ課題を解決し、図面の精度向上、品質改善、コスト削減を同時に達成できます。
【参考】CADmeisterの「3D検図」とは?
CADmeisterの3D検図の概要
CADmeisterの「3D検図(3DMODEL-CHECKER)」は、3D型設計データの検図作業を自動化し、データ計測や仕様確認を効率的かつ客観的に支援するシステムです。
このシステムでは、事前に正解となる検図データを用意し、そのデータを設計データの該当部分に自動的に位置合わせして、可否を自動判断します。また、Excelと連携することで、座標値を含む計算結果や部品の位置関係なども自動で確認でき、検図作業の精度と効率を大幅に向上させます。
具体的な確認項目としては、以下のようなものがあります。
- 部品部位のサイズ検証(座標値、外形サイズ、干渉確認など)
- 安全部品(例:フック、サイドピン)の座標値や必要な肉厚の確保確認
- 取付購入部品(座標値、データと部品表のサイズ差異確認及び員数確認)
- タップ・リーマ穴の穴径、深さ、位置の自動チェックと一覧表表示
- 車ボディへのハイテン材適用増によって、金型への設置が増加している鋼材(刃材)を検証する機能が実装され、大幅な作業工数の削減が実現できます。
具体的な確認項目は、以下のようなものがあります。- 鋼材サイズの自動計測(三方向)と発注サイズとの自動比較
- 外形と締付穴・位置決め穴との距離や、穴間距離の計測や、閾値との比較
- 複数刃材間の穴間距離計測による誤組防止確認
3Dモデルを利用することで、目視では難しい形状の把握や干渉チェックが可能となり、設計品質を飛躍的に向上させます。さらに、検図結果をExcel帳票に出力することで、検図作業の記録・管理も容易になります。
このようにCADmeisterの3D検図は、検図作業の効率化・自動化を実現し、設計工程全体の品質向上とコスト削減に貢献します。
より良い検図を行うためのコツ
検図精度を向上させるコツ
検図精度を向上させるためには、「確認基準の明確化」「チェック項目の標準化」「客観的視点の確保」が重要です。具体的なコツは以下の通りです。
- 確認基準の明確化
- あらかじめ明確な確認基準や仕様書を作成し、担当者間で共有することで、検図作業の判断基準を統一できます。
- チェック項目の標準化
- 検図作業で確認する項目をリスト化し、チェックシートを活用することで、確認漏れを防ぎ、精度向上につなげられます。
- 客観的視点の確保
- 設計者以外の第三者による検図を徹底し、設計者本人が気づかないミスや偏りを客観的に確認することが効果的です。
これらを意識することで、ミスを未然に防ぎ、検図の精度と品質を向上できます。
効果的に3D検図を活用する方法
3D検図を効果的に活用するためには「検図データの事前準備」「検図結果の活用」「Excel連携の利用」がポイントとなります。
- 検図データの事前準備
- 検図を自動化するには、事前に正確な基準となる3D検図データを準備することが重要です。これによりシステムが迅速かつ正確に判断できます。
- 検図結果の活用
- 3D検図による自動計測結果や差異確認結果を記録・共有し、改善につなげることで、次回以降の検図作業や設計の質が向上します。
- Excel連携の利用
- Excelと連携して座標値やサイズの計測結果を帳票として出力することで、データ管理が効率化され、検図作業の時間短縮と精度の向上を図れます。
以上を実践することで、3D検図技術を最大限活用し、設計の品質向上と効率化を同時に実現できます。
FAQ(よくある質問)
Q.検図はどのタイミングで行うべきか?
検図は「設計完了直後」と「製造開始前」のタイミングで行うことが最適です。
設計完了直後に初回検図を実施することで早期にミスを発見し、製造開始前に再確認することでトラブルを防ぎ、品質を担保できます。
Q.3D検図と2D検図の違いは?
3D検図と2D検図の大きな違いは、自動化が可能な否かです。
・2D検図は、データ活用が難しい2D図面(平面図、断面図等)を、手動で確認する手法です。
・3D検図は、データ活用が可能な3Dモデルを、3D設計手法を踏襲した自動化スタイルです。
具体的には、3D設計で利用されるアセンブり配置や、加工対象となる面や穴に付加されるシェード色(RGB)等を、Excel機能とを結びつけて自動化を実現しています。
3D検図はより精度の高い検証が可能です。
Q.検図にかかる時間を短縮するには?
検図時間の短縮には「検図項目の標準化」「3D検図システムの活用」「Excel連携による自動化」が有効です。
・検図項目を標準化することで確認作業を効率化できます。
・3D検図システムを導入すると、人手による作業を減らし、自動的かつ迅速に検図が可能です。
・Excelと連携したデータ管理を行うことで、作業負担が減り、効率的に検図作業を進められます。
Q.検図に資格や特別なスキルは必要か?
検図作業自体に特別な資格は必須ではありませんが、図面を読み解くための基本的な設計知識や経験が求められます。
また、特に精度が求められる場合は、専門的な設計知識や3D CAD操作のスキルがあれば、より効率的で正確な検図が可能となります。
まとめ
検図の重要性と適切な検図方法の再確認
検図は図面の正確性を確保し、製品の品質向上・製造トラブルの防止・コスト削減に不可欠な工程です。検図工程を省略したり不十分な確認で済ませたりすると、製造段階での問題が頻発し、大きな損失につながることがあります。
適切な検図を行うには、次のポイントが重要です。
- 明確な確認基準やチェック項目を標準化すること
- 設計者以外の第三者が客観的に検図を行うこと
- 3D検図技術を活用して、視覚的にわかりやすく精度の高い確認をすること
特に、3D検図技術の導入は検図作業を効率化し、ヒューマンエラーを最小化するため非常に有効です。
検図作業は単なる確認作業ではなく、製造工程全体の品質や生産性を大きく左右する重要な工程であることを再認識し、適切な方法で確実に実施しましょう。