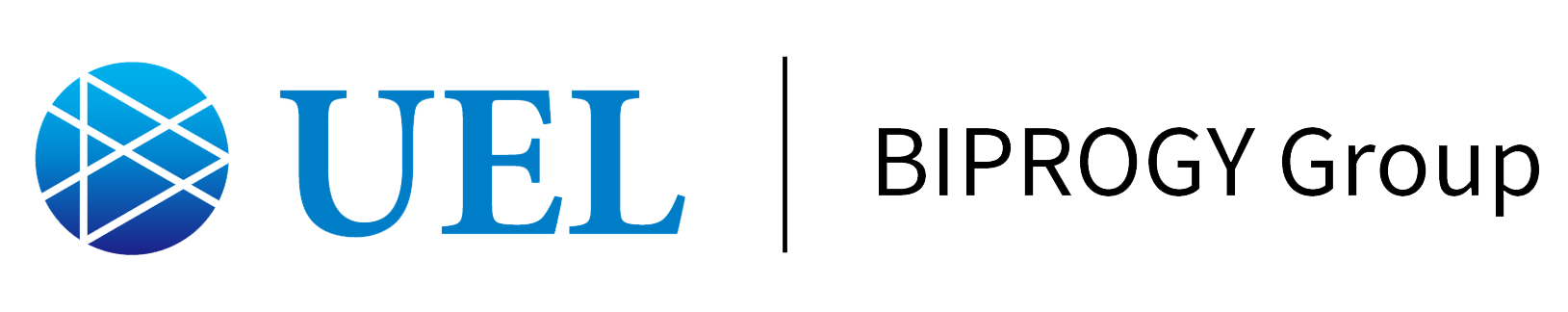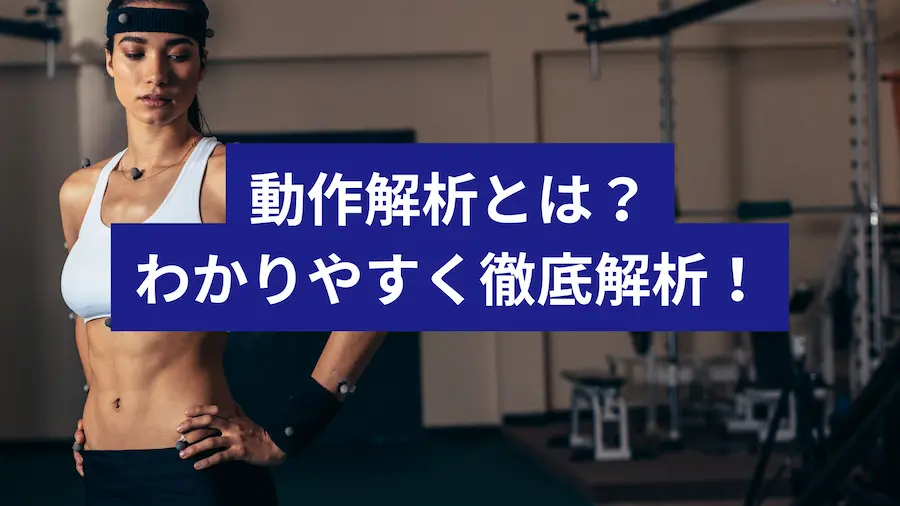動作解析って、そもそも何をするの?
「動作解析」という言葉を聞いたことはあっても、
何をどう解析するのか、少しわかりにくいと感じる方も多いでしょう。
動作解析とは、人や物の動きをデータとして捉え、見える化する技術のことです。
リハビリ、スポーツ、製造など、さまざまな現場で活用されています。
たとえばリハビリでは、歩行や腕の動きを計測して改善点を見つけたり、
スポーツではフォームを解析してパフォーマンスを高めたりします。
製造現場では、作業動作を記録して安全性や効率を検証することもあります。
本記事では、こうした動作解析の基本的な意味、方法、活用例を、初心者にもわかりやすく整理します。
専門用語をできるだけ使わず、身近な例を交えながら丁寧に解説していきます。
読み終えるころには、
自分の目的に合った動作解析のやり方が自然とイメージできるようになるでしょう。
この記事でわかること
この記事を読むと、次の内容がわかります。
- 動作解析とは何か(意味・目的・使われる場面)
- 動作解析と動作分析の違い(どんなときに使い分けるか)
- 動作解析の基本的な手順と流れ(初心者でも理解できるステップ)
- 動画解析やモーションキャプチャなどの代表的な手法
- どんな環境や条件で動作解析が可能か(可否・要件)
- おすすめの動作解析アプリやツールの選び方
- リハビリ、スポーツ、製造などでの具体的な活用事例
- 動作解析を始めるときに注意すべきポイント

監修・執筆:UEL株式会社編集部
UEL株式会社のTechデザイン企画部と現場に精通した社内有識者が監修・執筆しています。
目次
動作解析とは?
定義
動作解析とは、人や対象の動きを観察し、計測して数値化し、その結果をもとに改善や意思決定につなげるプロセスのことです。わかりやすく言えば、「動きをデータとして理解するための方法」です。
人の歩行やスポーツフォーム、作業中の姿勢など、目で見ただけでは捉えにくい動きの特徴をデータで明らかにします。たとえばリハビリでは、関節の動きを測定して改善点を見つけたり、スポーツではフォームを分析してパフォーマンスを高めたりします。製造現場では、作業動作を記録して安全性や効率を検証することにも使われます。
代表的な質問例としては「動作解析の目的は何ですか?」「動きの解析とは?」などがあります。これらの質問に共通する答えは、動きを科学的に理解し、改善や最適化につなげるという点です。
目的・対象
動作解析の目的は大きく五つに分けられます。それぞれが評価や改善などの行動と直結しています。
- 評価:動きの良し悪しや変化を数値で確認する
- 改善:課題のある動作を修正し、効率的な動きを導く
- 教育:正しい動作を可視化して共有・指導に活かす
- 研究:動作や身体の仕組みを明らかにする
- 設計:製品や機構の動きをシミュレーションして最適化する
動作解析の対象は幅広く、リハビリ、スポーツ、製造工程、教育、研究など多岐にわたります。
リハビリの現場では「リハビリにおける動作解析とは?」という質問に見られるように、歩行や日常動作の改善度を数値で評価する目的で用いられます。製造や工程管理では「工程解析とは何ですか?」という疑問にあるように、作業姿勢や手順を解析して効率化や安全性向上を目指します。
つまり動作解析は、「動き」を中心に改善を繰り返すための基盤的な技術といえます。
関連用語の整理
「動作解析」という言葉の周辺には、似た用語が多く存在します。それぞれの意味や使われ方の違いを理解しておくと、情報を整理しやすくなります。
| 用語 | 意味・特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 動作分析 | 動きを観察して特徴や課題を整理する定性的な分析。主観的な評価を含む。 | リハビリ、教育、心理分野 |
| 動態解析 | 物体や身体の運動(位置・速度・加速度など)を時間軸で解析する。 | 工学、生体力学 |
| 動解析 | 動態解析を略した表現で、より専門的な数値解析を指すことが多い。 | 工学、研究分野 |
| 動画解析 | 撮影した動画から動きを抽出・分析する手法。AIや画像処理技術を使う。 | スポーツ、製造、教育 |
| 画像解析 | 静止画像を解析して形状や位置などを把握する手法。 | 設計、品質管理、AI解析 |
| モーションキャプチャ | センサーやマーカーを使って3次元的に動作を記録する技術。高精度な再現が可能。 | リハビリ、スポーツ、アニメーション |
これらの用語は互いに重なり合いながらも、扱うデータの種類や目的によって使い分けられます。
たとえば「モーションキャプチャーの特徴は?」という質問に対しては、「3次元空間で動きを正確に記録し、高精度な解析ができる技術」と答えられます。
このように動作解析は、動作分析や動画解析などの個別手法をまとめる、総合的な“動きの理解”の枠組みと言えます。
「解析」と「分析」の違いと使い分け
「解析」と「分析」はどう違うのか
「解析」と「分析」という言葉は似ていますが、意味と使われる場面には明確な違いがあります。
どちらもデータを扱う点では同じですが、目的や深さが異なります。
解析は、物事の構造や仕組みを「分解して理解する」ことを指します。
対象を細かく分けて原因や関係性を明らかにし、根本的な仕組みを捉えるのが目的です。
一方、分析は、集めたデータを整理し、特徴や傾向を「把握して判断する」ことを意味します。
結果を比較したり、意思決定に活かしたりする目的で使われます。
つまり、
- 解析:なぜそうなるのかを知りたいとき
- 分析:どうすれば良くなるかを決めたいとき
という使い分けが基本です。
代表的な質問「解析と分析はどう使い分けます?」に対して答えるなら、
「解析は構造の理解、分析は意思決定のため」とまとめられます。
使い分けのガイド
両者の違いを目的・データの性質・アウトプットの粒度で整理すると、次のようになります。
| 項目 | 解析 | 分析 |
|---|---|---|
| 目的 | 原因の追究、仕組みや原理の理解 | 状況の把握、改善や判断のための評価 |
| データの性質 | 時系列・3D座標・センサーなど、構造を持つデータ | 数値・画像・結果データなど、比較や傾向を見るデータ |
| アプローチ | 分解して理解する(理論・モデル重視) | 整理して判断する(結果・傾向重視) |
| アウトプット | 構造の解明、メカニズムの説明 | 可視化、指標化、改善提案 |
| 使用例 | 動作解析、構造解析、CAE解析 | 動作分析、業務分析、データ分析 |
解析は“なぜ起きたのか”を明らかにし、分析は“どう対応するか”を決めるために行われます。両者は対立するものではなく、むしろ連続した流れの中で使われます。
たとえば動作解析では、まず関節や姿勢のデータを解析して構造を理解し、その後に結果を分析して改善方針を立てます。このように解析と分析は、プロセスの前後関係としてつながっています。
使い分けチェックリスト
どちらを使うべきか迷ったときは、次の3つの観点で判断するとわかりやすいです。
1. 目的を確認する
- 原因や仕組みを理解したい → 「解析」
- 判断や改善に活かしたい → 「分析」
2. データの種類を見る
- 時系列、動画、3Dデータなど、構造を持つもの → 「解析」
- 数値表、グラフ、統計的データなど → 「分析」
3. 求める結果を意識する
- 目的が「可視化」「仮説検証」「設計変更」なら → 「解析」
- 目的が「傾向の把握」「成果の評価」「意思決定」なら → 「分析」
このように、目的とデータの性質、求める結果を整理することで、自然に正しい言葉を選べます。
実務での使い分けの例
リハビリの現場では、関節の動きを計測して仕組みを理解する段階が「解析」、その結果を基に改善点を判断する段階が「分析」です。
スポーツでは、フォームを3Dで解析し、どの動作が記録に影響するかを分析します。製造現場では、工程の動作を解析して機構を理解し、分析によって改善策を立てるという流れになります。
このように、解析と分析は目的によって役割が異なりますが、最終的には「より良い結果を導く」ための両輪です。
動作解析の方法・手順
基本の流れ(5ステップ)
動作解析は、目的を明確にしてからデータを集め、結果を確認・改善するまでの一連の流れで進めます。以下の5つのステップが基本です。
1. 目的を決める(何を知りたいか)
最初に「どんな動きを、なぜ解析したいのか」を明確にします。目的が曖昧だと、必要なデータの種類や方法も決まりません。
たとえば、
- 歩行動作を数値で評価したい
- スポーツフォームを改善したい
- 作業中の姿勢を分析して効率化したい
など、目的に合わせて解析の方針を設定します。
2. データを記録する(動画・センサーなど)
次に、対象の動作を記録します。動画カメラ、スマートフォン、モーションセンサーなど、目的に応じて使うツールが変わります。
リハビリや研究現場では複数のカメラで撮影することもあり、製造分野では作業中の動作を記録して後から解析するケースもあります。記録の際は、撮影角度・明るさ・背景の一貫性が重要です。
3. データを解析する(角度・速度・タイミングを数値化)
記録したデータを解析し、動作の特徴を数値化します。角度、速度、タイミング、加速度などの指標を算出し、動きの特徴を明らかにします。
動画解析ソフトやモーションキャプチャを使えば、関節の動きや身体の軌跡を3Dで表示し、どの部分にズレや非対称があるかを可視化できます。
4. 結果を確認する(グラフやレポートで可視化)
解析結果は、グラフや時系列チャート、レポートなどで確認します。視覚的に理解しやすくすることで、課題や改善点をすぐに把握できます。
リハビリでは「正常歩行との差」や「可動域の変化」をグラフで比較し、スポーツでは「動作の再現性」や「タイミングのズレ」をチェックします。
5. 改善・再評価する
最後に、解析結果をもとに改善を行い、再度評価します。動作解析は一度きりではなく、改善と検証を繰り返すサイクルが基本です。
リハビリなら訓練内容の調整、スポーツならフォーム修正、製造なら作業動線の見直しなど、目的に応じた改善を実施します。再評価によって効果を確認し、最適な動作を定着させます。
よくある質問
Q1. データ解析の手順は?
A. 目的設定 → 記録 → 解析 → 結果確認 → 改善・再評価 の5段階です。それぞれのステップを順に行うことで、動作を科学的に理解できます。
Q2. 動作分析の手順は?
A. 観察・記録・評価の3段階が基本です。動作解析と異なり、分析は「評価や判断」に重点を置きます。データを数値化する前に、まず動作の流れや姿勢を観察して特徴を整理します。
Q3. リハビリの評価手順は?
A. 評価目的を明確にし、歩行や基本動作を撮影・記録したうえで解析します。得られた数値(関節角度・速度・バランスなど)を基に改善計画を立て、再度測定して変化を確認します。この繰り返しが、機能回復や動作改善の精度を高めるポイントです。
どこまでできる?動作解析の可否・要件チェック
「自分でも動作解析ってできるの?」「特別な機材が必要?」そう感じる方は多いでしょう。
動作解析は、目的と環境によってできる範囲が大きく変わります。ここでは、どんな条件がそろえば解析が可能になるのかをわかりやすく整理します。
自分でもできる動作解析とは
最近は、スマートフォンやタブレットのカメラを使って簡単な動作分析ができるアプリも増えています。たとえば、フォームの角度を測定したり、動画をスロー再生して比較したりといった解析は、無料ツールでも可能です。
ただし、関節の正確な角度測定や3D動作の再現といった高度な解析を行う場合は、モーションキャプチャや専用センサーなどの専門機材が必要です。
つまり、
- 目的が「フォームの確認」程度ならスマホでも十分
- 研究や設計レベルの精度を求めるなら専門環境が必要
というように、求める精度によって必要な条件が変わります。
代表的な質問には、「動作分析ができるアプリは?」「条件や要件はある?」といったものがあります。
これらの答えは、目的と環境を整理すれば自然に見えてくるのです。
動作解析を行うための基本条件
動作解析を行う際は、以下の4つの視点で条件を確認します。
これは「何ができて、何ができないか」を判断するためのチェックリストです。
- 対象:誰(何)を解析するか
人・動物・機械など、対象によって必要なデータ形式が変わります。
たとえば、人の歩行を解析する場合と、機械の動作を解析する場合では計測方法が異なります。 - データ:どんな情報を扱うか
動画・センサー・3D座標など、入力データの種類を決めます。
カメラ1台の映像だけでも解析は可能ですが、正確な空間情報を得たい場合は複数カメラやセンサーが必要です。 - 環境:どんな場所で記録するか
撮影環境も結果に大きく影響します。
カメラの位置、照明の明るさ、撮影距離などを整えることで、動きの検出精度が上がります。
背景が複雑だと誤認識の原因になるため、シンプルな環境が理想です。 - 目的:何のために解析するか
目的が「評価」「研究」「教育」「改善」などによって、必要なレベルが変わります。
- 改善目的なら動画解析アプリでも十分
- 研究・教育目的なら3Dモーションデータが望ましい
- 設計や工程改善には、CAEや動作シミュレーションの導入が必要
これら4つの条件を整理すると、自分の環境でどこまでの解析が可能かが明確になります。
環境別の実現イメージ
| 目的 | 可能な範囲 | 必要なツール例 |
|---|---|---|
| 日常動作の確認・練習 | 〇(スマホ・無料アプリ) | 動作分析アプリ、動画撮影機能 |
| スポーツフォームの評価 | ◎(動画+角度測定アプリ) | 解析アプリ、スロー再生、比較機能 |
| リハビリの進捗評価 | ◎(センサー・複数カメラ) | 医療向け動作解析システム |
| 研究・製造工程の解析 | ◎(高精度3D解析) | モーションキャプチャ、CAE解析ツール |
どのレベルを目指すかによって、必要な環境や費用が変わります。まずは自分の目的に必要なデータ精度を見極めることが最初のステップです。
次のステップ:あなたの環境で動作解析ができるかチェック
ここまでの内容をもとに、次の項目を自分の環境と照らし合わせてみてください。
- 対象は人・動物・機械のどれか?
- 動きを記録できるカメラやセンサーはあるか?
- 明るさ・背景・撮影距離など、解析に適した環境が整っているか?
- 解析の目的は「評価」「改善」「研究」のどれか?
これらを確認することで、「自分の環境で動作解析ができるか」が判断できます。
この章の最後に、サイト内で利用できる「動作解析の可否診断ツール」(チェック式フォーム)への導線を配置すると効果的です。
読者が次の行動(ツール利用・比較・導入検討)に自然に進める導線になります。
動作解析で使われる主な技術とツール
動作解析では、目的や環境に応じてさまざまな技術が使われます。ここでは代表的な二つの手法「動画解析・画像解析」と「モーションキャプチャ」について紹介します。
どちらも「動きをデータとして記録・分析する」点は同じですが、得られる情報の深さや精度に違いがあります。
動画解析・画像解析
動画解析とは、カメラで撮影した映像を使って動きを分析する方法です。
人の目で見た動作を、ソフトウェアがフレーム単位で解析し、位置や角度の変化を自動で抽出します。
たとえば、
- 歩行時の関節角度をフレームごとに数値化する
- 投球フォームの速度や角度を比較する
- 作業姿勢の安定性を評価する
といった使い方ができます。
スマートフォンやタブレットのカメラでも撮影できるため、リハビリやスポーツ指導の現場で広く利用されています。AIを活用した動画解析アプリでは、人物の動きを自動で検出してグラフ化したり、理想フォームとの違いを可視化したりすることも可能です。
一方、画像解析は静止画像を対象とした解析技術です。
動作の瞬間を切り取って姿勢や角度を確認するのに向いており、製造業や設計、AI学習データの作成などにも使われます。
動画解析と画像解析は、どちらもカメラ映像を活用した“非接触型の解析手法”という点で共通しています。ただし、動画解析が「動きの流れ」を重視するのに対し、画像解析は「形状や位置の正確さ」を重視する点が異なります。
代表的な質問としては、「動画解析とは?」「画像解析とは何ですか?」などがあり、どちらも“動きをどう可視化するか”という関心から生まれた疑問です。
動画解析は、動きを時間軸で捉える方法。
画像解析は、動きを一瞬の形から理解する方法。
このように覚えると違いがわかりやすいでしょう。
モーションキャプチャ
モーションキャプチャ(Motion Capture)とは、人の体の動きを3D空間で記録する技術です。被験者の体にマーカーやセンサーを取り付け、カメラやセンサーユニットでその位置情報を正確に捉えます。取得したデータをもとに、動作を立体的に再現・解析できます。
モーションキャプチャの大きな特徴は、「3Dでの精密な再現」と「時間軸での動きの連続性」です。
そのため、動きの細部まで高精度に確認でき、関節や姿勢のわずかな違いも見逃しません。
この技術は、リハビリやスポーツ分野ではもちろん、アニメーションや映画制作など、エンターテインメント分野でも広く活用されています。たとえば、映画の登場人物の自然な動きやゲームキャラクターのリアルな動作は、モーションキャプチャによって作られています。
また医療・リハビリの分野では、歩行や上肢の動きを3Dで記録し、改善計画を立てるための定量データとして利用されます。スポーツではフォームの最適化、製造業では作業の安全性評価などにも応用されています。
代表的な質問としては、「モーションキャプチャーの特徴は?」「モーションキャプチャーの元祖は誰ですか?」があります。これらの疑問に対しては、次のように答えられます。
- 特徴:動きを3Dで記録でき、精密な姿勢データを取得できる。
- 起源:映画制作や工学研究など、20世紀後半の技術開発から発展した。
モーションキャプチャは、動作解析の中でも最も高精度で再現性の高い手法といえます。ただし、機材や環境の準備が必要なため、専門施設や研究機関での利用が中心です。
アプリ・ツールの比較と選び方
「動作解析をしたいけれど、どのアプリやソフトを使えばいいのかわからない」そんな疑問を持つ人は少なくありません。
動作解析ツールは目的や使用環境によって向き・不向きがあり、どの動作を、どのレベルで分析したいかによって最適な選択が変わります。
ここでは、動作解析アプリ・ツールを選ぶときの判断ポイントを整理します。
動作解析ツールの選び方の基本
まず、動作解析ツールを選ぶ際に確認すべき要素は次の4つです。
- 対応する動作
歩行・上肢・スポーツフォーム・工程動作など、ツールごとに得意分野があります。
リハビリ用途であれば歩行や日常動作、スポーツ用途であればフォームや姿勢に強いものを選びます。 - データ形式
動画、センサー、3D座標など、入力データの種類を確認します。
動画だけで解析できるものもあれば、モーションセンサーや3Dカメラを組み合わせて高精度に測定できるタイプもあります。
目的に応じて「どの形式のデータを扱えるか」を明確にしましょう。 - 分析指標
角度・速度・距離・スコアなど、出力できる指標の種類もツールによって異なります。
たとえば、フォームの改善が目的なら角度やリズム、研究用途なら時系列データや統計指標を出力できるものが便利です。 - コスト・導入難易度・操作性
アプリによってはスマートフォン1台で完結するものもあれば、
専用機材やライセンス契約が必要なプロ向けソフトもあります。
導入コストだけでなく、使いやすさやサポート体制も比較のポイントです。
用途別のおすすめタイプ
| 目的 | 向いているツールタイプ | 特徴 |
|---|---|---|
| リハビリ・医療 | センサー連携型、歩行解析システム | 関節角度やバランスを定量化できる。医療現場で実績あり。 |
| スポーツ・教育 | 動画解析アプリ | スマホで撮影し、フォーム比較や角度測定が簡単にできる。 |
| 製造・工程管理 | 動画+AI解析ツール | 作業姿勢や動作効率を数値化し、安全・品質改善に役立つ。 |
| 研究・設計 | モーションキャプチャ、CAE解析 | 高精度の3Dデータ取得が可能。分析の自由度が高い。 |
具体的な選定ステップ
- 目的を明確にする
どんな動作を、どのレベルの精度で解析したいかを最初に整理します。 - 環境を確認する
使用する場所(室内・屋外)、撮影環境(照明・カメラ台数)を把握します。 - ツールの対応範囲を確認する
目的の動作に対応しているか、扱いたいデータ形式をサポートしているかを確認します。 - 出力と操作性を比較する
結果をレポートやグラフで見たいのか、数値データとして保存したいのかによって適したツールが異なります。
試用版やデモを利用して、操作性を実際に確かめるのがおすすめです。
判断のコツ
「おすすめの動作解析アプリは?」という質問に対しては、一概に“これがベスト”とは言い切れません。
大切なのは、目的と環境に合ったものを選ぶことです。
たとえば、
- 手軽にフォームを比較したい → スマートフォン動画解析アプリ
- 精密な歩行データを取得したい → センサー連携型システム
- 研究や設計に使いたい → 3Dモーションキャプチャ/CAE解析ソフト
このように、自分の目的に合わせてツールの精度と機能を見極めることが、失敗しない選び方のポイントです。
選定後の注意点
ツールを導入した後は、
- 撮影条件を一定に保つこと
- データの記録方法を統一すること
- 結果を過信せず、現場の観察と併用すること
この3点を意識することで、解析の精度と再現性が安定します。
よくある質問(FAQ)
ここでは、動作解析に関してよく寄せられる質問にお答えします。基礎的な疑問から実践的な内容まで、簡潔にまとめました。
Q1. 動作解析の目的は?
動作解析の目的は、人や物の動きをデータとして可視化し、評価・改善に活かすことです。
リハビリやスポーツでは、動きを正確に数値化することで、課題の発見や効果測定ができます。
製造や研究分野では、作業効率や安全性の向上にも利用されます。
Q2. 動作解析と動作分析の違いは?
動作解析は、動きを数値化して構造的に理解する技術的手法です。一方、動作分析は、動きの特徴を観察して評価する行為を指します。解析が「なぜそうなるのか」を追究するのに対し、分析は「どのような特徴があるか」を整理・判断するという違いがあります。
つまり、動作解析=“科学的な分解”、動作分析=“評価と判断”という関係です。
Q3. モーションキャプチャと動画解析の違いは?
モーションキャプチャは、体にマーカーやセンサーをつけて3Dで動作を記録する方法です。動きを立体的に再現でき、関節の角度や位置を高精度で取得できます。
動画解析は、カメラで撮影した映像から動きを2D的に解析する方法です。特別な機材がなくても利用でき、スポーツや教育現場などで手軽に使われます。
要するに、モーションキャプチャは「精密な3D計測」、動画解析は「手軽な2D可視化」と言えます。
Q4. リハビリやスポーツでの効果は?
リハビリでは、動作解析を使うことで歩行や上肢の回復状況を数値で把握できます。これにより、どの訓練が効果的かを明確に判断でき、治療の精度が高まります。
スポーツでは、フォームや動作リズムを解析することでパフォーマンスの最適化やケガの予防につながります。数値をもとに改善することで、選手本人が自分の動きを客観的に理解しやすくなります。
Q5. 動作解析は個人でもできる?
はい、近年はスマートフォンやタブレットで簡易的な動作解析が可能です。無料または低価格のアプリを使えば、フォーム比較や角度測定などの基本的な分析ができます。ただし、正確な3D解析や専門的な計測を行う場合は、専用のカメラやセンサーが必要です。
まずは「動画を撮影して動きを観察する」だけでも、十分な気づきが得られます。目的に応じて、必要な精度に合ったツールを選ぶのがポイントです。
Q6. どんなデータが必要?
動作解析に必要なデータは、目的によって異なります。一般的には以下の3種類のデータが使われます。
・動画データ:スマートフォンやカメラで撮影した映像
・センサーデータ:加速度や角速度などを測る装置から取得
・3D座標データ:モーションキャプチャなどで体の位置を数値化
歩行解析などでは、カメラ1台の映像でも可能ですが、より精密な解析には複数カメラやセンサーを組み合わせることで精度が向上します。
まとめ:動作解析は「動きを理解して改善につなげる」技術
動作解析の本質は、「動きを見える化し、次の一歩を導くこと」にあります。私たちは普段、感覚や経験で「動き」を判断しがちですが、動作解析ではそれをデータで理解し、根拠をもって改善へつなげることができます。
リハビリでは、回復の進み具合を数値で確認し、スポーツではフォームやバランスをデータで比較し、製造現場では作業効率や安全性を解析して最適化する。
分野は違っても、共通しているのは「データで動きを理解し、改善の方向性を見出す」という考え方です。
動作解析は、専門的な研究だけでなく、現場の判断・教育・日常の改善にも応用できる「実践的な技術」と言えます。
どんな分野でも、目的は同じです。動きを正確に理解し、改善を重ねて、より良い成果へ導くこと。それが動作解析の真価です。